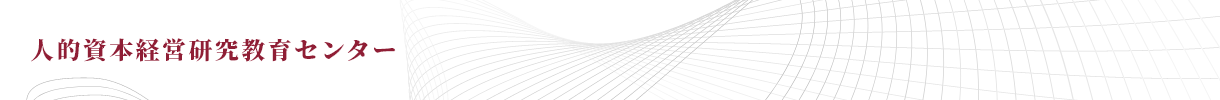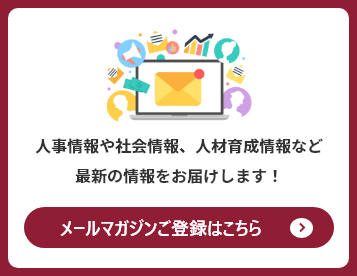2024.02.28
マネジメントトレンドの変遷と人的資本経営

マネジメントのトレンド
人事管理(を含めたマネジメント)の議論(学術的なものも、実践的なものも共に含みます)のトレンドを、大まかに整理すると、おおよそ表1のようになると思います。
重化学工業が進行し、独占資本主義の段階にあった当時のアメリカでは、経営者による従業員の搾取と、監督者の恣意に基づく成り行き管理が横行していました。そのような経営の現場に、「科学」な視点を導入したのが、F.W.テイラーの科学的管理法です。作業方法や仕事量、作業時間などの標準化、差別的出来高給など、いくつかの重要な考え方を提示したテイラーの議論は、組織を機械のアナロジーで捉え、そこで働く従業員を、もっぱら賃金のために働いており、自らの意思はなく監督者の命令に受動的にしたがう経済学的で機械的な存在とみなすという特徴を持ったものでした。
そのような組織観・個人観を打ち破って、マネジメントに関する新たな視点を提供したのが人間関係論です。この研究の主導者であるE.メイヨーやF.J.レスリスバーガーらは、組織の中の個人は、集団における安定感や所属感を求める、社会的・心理的な存在である、という(素朴ではありますが)重要な指摘を行いました。社内キャリアカウンセリングや各種福利厚生など、今日の人的資源管理実践に大きな影響を与えたのも、この人間関係論でした。
1950年代に入るとオペレーションズ・リサーチ(OR)、1960年代後半からはコンティンジェンシー理論といった議論が、マネジメントの議論を席巻することになります。ORは、第二次世界大戦中の軍事的要請の中で発展し大戦後に産業の分野に導入されたものであり、種々の計画における最適な条件を数学的なアルゴリズムを用いて解明する方法。コンティンジェンシー理論は、「環境が異なれば有効な組織構造やマネジメントのあり方が異なる」というアイデアのもとに、高い成果をあげる組織のあり方を検討したものでした。いずれも組織=合理的に設計可能なシステムという前提に立って、システム合理性の観点から、個人をどのように配置し、動かせば良いか、という共通した組織観・人間観を持っていました。
1980年代に入ると、T.J.ピーターズとR.H.ウォーターマンによるベストセラー『エクセレント・カンパニー』の出版を契機とした組織文化論が登場します。共有された価値観や規範、社員のコミットメントといった組織のソフトな側面こそが、組織マネジメントにおいて重要であり、組織の成果につながるのだ、という主張であり、その典型例として注目されたのが、日本企業でした。
表1.100年スパンでみたマネジメントのトレンド
| トレンド | 年代 | 関連するキーワード | アプローチの テイスト |
|---|---|---|---|
| 科学的管理 | 1900〜1920年頃 | 作業の標準化,差別的出来高級,流れ作業方式 | クール |
| 人間関係論 | 1920〜1960年頃 | 人間関係,従業員福祉,福利厚生 | ウォーム |
| 組織の合理化 | 1960〜1980年頃 | 自動化,オペレーションズリサーチ ,有機的組織/機械的組織 | クール |
| 組織文化/コミットメント | 1980〜1990年頃 | 文化,ビジョン/理念,コミットメント | ウォーム |
| 戦略の実現と成果主義 | 1990年〜 | 戦略との連動,成果主義,目標管理,BPR, バランストスコアカード | クール |
| 多様性と全体性 | 2010年〜 | パーパス,人的資本,多様性,従業員エクスペリエンス,ティール組織 | ウォーム |
クールとウォームの循環
ステファン・R・バーリー(スタンフォード大学)とギデオン・クンダ(テレ・アビブ大学)は、このような一見バラバラに見えるトレンドの推移が、実は、ウォームアプローチとクールアプローチという、2つのコントロールメカニズムの間の循環の歴史であることを指摘しています(厳密にいえば、彼らはrationalとnormativeという言葉を用いているのですが、少し堅苦しいので、ここではこのように呼ぶことにします)。
クールアプローチとは,組織を機械やコンピュータのアナロジーで捉え、マネジメント基準として「合理性(主として経済合理性)」を重視するマネジメントのあり方を指します。この場合、組織を構成する社員は、機械の一部を構成するパーツとして捉えられることになります。対して,ウォームアプローチにおいて組織は、生物など、よりダイナミックなアナロジーで捉えられます。ここにあって従業員は,価値を共有し,組織体に対して感情的にコミットする社会的・心理的な主体とみなされ,そした側面こそが,彼(女)らを管理するために重要だと考えられます。
このような視点からみると、一見バラバラに見える人事管理の推移を、クールアプローチ→ウォームアプローチ→クールアプローチ→ウォームアプローチ・・・といった循環の歴史と捉えることができる、とバーリとクンダは主張しているのです。
ただ、1992年に発表されたバーリとクンダの研究で紹介されているのは、表1の組織文化/コミットメントのところまでです。その後、経営学においても経営の現場においても、ビジネスプロセス・リエンジニアリング(BPR)やバランスト・スコア・カード(BSC)といった、新たなマクロ・マネジメント手法が登場しました。人的資源管理においても、成果主義賃金制度のような個人の業績達成に関わる議論、さらには戦略的人的資源管理や目標管理といった組織全体の目標達成と個人の貢献とを連結させるような議論が盛んになりました。いずれも、種々の成果の実現に向けて、組織を合理的にデザインし、組織の戦略なり目標の達成に向けて個人を戦力化するための試みであるという意味で、クールアプローチとしての色合いが強いものだといえるでしょう。
直近のトレンド
直近10年ほどの間に登場し、注目されているのは、人的資本経営、パーパス、多様性と包摂、従業員エクスペリエンス、心理的安全性、ティール組織といったワードでしょうか。一見すると、新しい概念の無秩序な氾濫のようにも見えるのですが、私のみるところこれらの背後には、(1)多様性と(2)全体性という重要な共通点があります。多様性とは、文字通り、組織の中にジェンダーや国籍、経験、価値観といった意味で多様な個人が参入するようになるし、またそうあるべきだということ。全体性とは、個人が「雇用された働き手」としてだけでなく、さまざまな側面を持った複合的な存在であることを認める、ということです。例えばそれは、「給与のために働く、〇〇社の社員」というだけでなく、「2児の父親/母親」であり、かつ「週末に仲間とのサッカーに興じること」を生き甲斐としている、といったことを認めるということです。
上記のような1つ1つのワードの中には、一時的な流行でありバスワードとしての性格が強いものが少なくないわけですが,それらの背後には,人間関係論などに通ずるウォームアプローチの発想があるように思います。今日のトレンドもまた、クールとウォームの循環の中で理解できる、ということです。
人的資本経営を相対化する
いま注目されている人的資本経営もまた、このような大きなトレンドの中で登場したものであるし、またそのように理解するべきだと私は思います。それは具体的に2つの意味においてです。 第1に、私たちは、「人的資本」という言葉の持つ意味を、多様性と全体性という大きな枠組みの中で理解する必要がある、ということ。例えばそれは、短期的な成果に直結する狭義の人的資本(例えば、Knowledge, Skill, Ability, and Other characteristics: KSAOs)にとどまらない、組織や個人が持つ資本の豊かさ(例えば、心理的資本、文化資本、社会関係資本)にも注目する、といったことです。
第2に、今日私たちが注目し、熱狂しているものの少なくとも一部は、私たちにとって「過去の焼き直し」である可能性がある、ということを自覚しなければならないということです。例えば、今日注目される「パーパス」に関わる議論の多くが、1980年代以降の組織文化/コミットメントの議論の中ですでになされていますし、少し前に流行った「ティール組織」の議論は、少なくとの私の目には、組織の合理化の時代に登場した有機的組織のアイデアとかなるところ大です。個人の「全体性」に至っては、すでに1920年代に人間関係論者によって指摘されています。
ここで申し上げたいのは、今日注目されるトレンド全てに価値がない、ということでは決してありません(正直に申し上げて、そういうものもあることはあるのですが)。これらの重要性を信じているからこそ、それらを一時的な流行で終わらせないように、骨太な議論が必要ではないかと考えているのです。その一端を、人的資本経営研究教育センターの一員として担えれば幸いです。
関連リンク
・神戸大学MBA教授陣に学ぶ「経営学の実践知」
ビジネス課題の解決にあたる人財の育成を目的に、現代経営学研究所(RIAM)と共催で企画した、厳選した8科目を学ぶプレMBAプログラム。