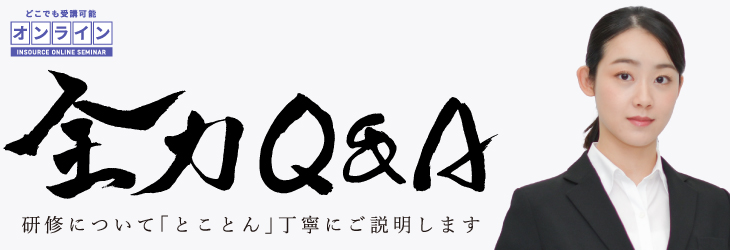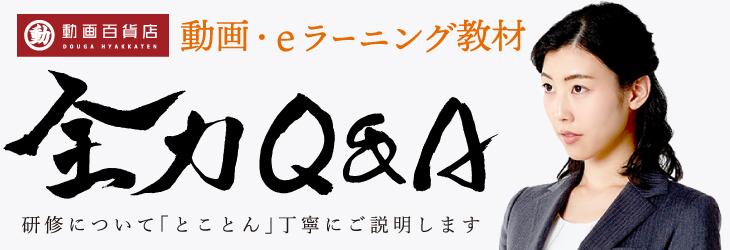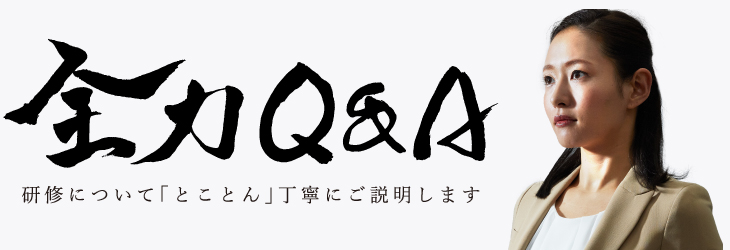2,755問の質問に全力でお答え!
{{trainingName}}
お客さまから「{{trainingName}}」に多く寄せられるご質問を掲載しております。
インソース社員が研修のプロとして丁寧に回答しておりますので、気になる点が少しでも解消されるよう、ご活用いただければ幸いです。
インソースには、毎年、数千件以上のお問合せがあり、様々なお客さまから多種多様なご質問をいただきます。本ページでは、それらのご質問にお答えする「Q&A」形式で、各種研修・サービス内容をひたすらに深掘りしてご説明します。
お客さまの「気になること」「知りたいこと」が少しでも解消されるよう、「研修のプロ」であるインソース社員が全力で丁寧に回答しております。各種研修・サービスのご検討にあたって、ぜひお役立てください。
※知りたい事柄について記載がない場合、ぜひお問合せください。迅速にお答えいたします
- 本サービスはGPTsにて作成しております
- 別途ChatGPTの有料プランアカウントが必要となります