研究開発部門、技術開発部門、事業開発部門、経営企画部門の方など
トップページ > 公開講座 > 公開講座 テーマ別研修ラインナップ 人事/総務/財務/法務研修 > 技術基点の新規事業の失敗・成功要因、実際のツボとは? ~製造業で培ったアナログ技術を活かした事例から学ぶ~
技術基点の新規事業の失敗・成功要因、実際のツボとは? ~製造業で培ったアナログ技術を活かした事例から学ぶ~

No. 99K251490
受講対象target
講義のねらいoutline
イノベーションとは、発明(0→1)ではなく既知と未知の結合と経済性である、と学者シュンペーターがイノベーション理論の中で結論付けています。 「自社技術(既知) x 社外にある未知技術」 を組み合わせ、多くのお客様に御愛顧頂ける商品やサービスを提供(経済性)する。 シンプルに新規事業を捉え、実践検証しながら失敗を減らして成功体験を積み、継続的で組織的な学習さえできれば、どの企業でも創出することは可能だと考えています。
しかしながら、そこには技術的難易度やコストダウン、経営マネジメントなど社内に数多の壁や敵がおり、社外にもスピード早いスタートアップや投資意欲高い海外企業の存在もあり、既存事業とは違う戦いの厳しさがあると思います。
それでも、私は日本の継続的な競争優位を築くことにおいて、技術テクノロジー偏重でもなく、思いつきのアイデア商品のような短命な事業でもなく、自社の強みや培ってきたアナログ技術が生きる新規事業を創出することこそ、必要不可欠であると考えています。本講演では、製造業の新規事業の実践結果から得たノウハウだけでなく、実際の成功事例を交えながらお伝えしたいと思います。
主催団体organizer
本コースは、一般社団法人企業研究会が主催しております。
研修プログラム例program
1.実践を通じてわかった「新規事業のツボ」とは?
1-1.成功確率を上げる「新規事業の方程式」とは?
1-2.技術基点の新規事業に対する「誤解」を解く
1-3.過去事例から学んだ「6つの失敗要因」
1-4.実践経験から学んだ「6つの成功要因」
2.実践的な「新規事業の開発プロセス」とは?
2-1.長年の実践から見えた「新規事業プロセス全体像」
2-2.成否のカギを握る、新規事業立ち上げ前のツボ
2-3.顧客課題ドリブンの徹底こそ、新規事業の探索の命
2-4.成功に欠かせない3つの視点のPoC
2-5.何屋になるのか? ビジネスモデルの一番のキモ
2-6.点を線に、線を面に、事業計画におけるシナリオの重要性
2-7.ローンチしてからが本番、量産効果の呪縛から逃れろ
3.経験・知見が活きにくい「新規事業のマネジメント」をうまくやるには?
3-1.ステージで変わる「新規事業のチーム体制」
3-2.ステージで変わる「新規事業のマネジメントのやり方」
3-3.「型」と「失敗」から学ぶ継続的な人材育成と組織学習
4.新規事業の実例から学ぶ「日本製造業の技術基点の新規事業の実際」
4-1.大手自動車部品メーカー:コア技術基点に将来事業の柱をつくる
4-2.中堅電器メーカー:B2Bからの脱却し、B2Cで新ビジネスをつくる
5.質疑応答
注意事項notice
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。
【事前に必ずご確認の上お申込みください】
※事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
※お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
※お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。
◆受講形式のご案内
【オンライン受講の方】
オンラインには、開催形式が<zoom開催>と<LIVE配信開催>の2つがございます。
開催日や研修内容により、開講形式が異なります。
該当される開催形式のご案内をご確認の上お申込ください。
ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。
事前に下記の「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。
<zoom開催> 講師の方や他にご参加の方とのやり取りが可能
動作確認ページ
<LIVE配信開催> ご聴講のみ
動作確認ページ
ID livetest55
PASS livetest55
※LIVE配信は、企業研究会様の協力会社である、株式会社ファシオ様のイベント配信プラットフォーム「Delivaru」を使用されております。
お客様の会社のネットワークセキュリティによってはご視聴ができない場合もございますので必ず【動作確認】をしていただいた後に、お申込ください。
※オンライン受講の場合、視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催日の1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
【会場受講の方】
お申込時に、会場情報(住所・アクセス方法)をご確認ください。
筆記用具はご自身でご準備ください。
お申込み後のキャンセルにつきましてはこちらをご覧ください
スケジュール・お申込み
(オンライン/セミナールーム開催)schedule・application
オンライン開催
講師instructor
イノベーションマネジメント(株)執行役員 パートナーコンサルタント 井口佳一 氏
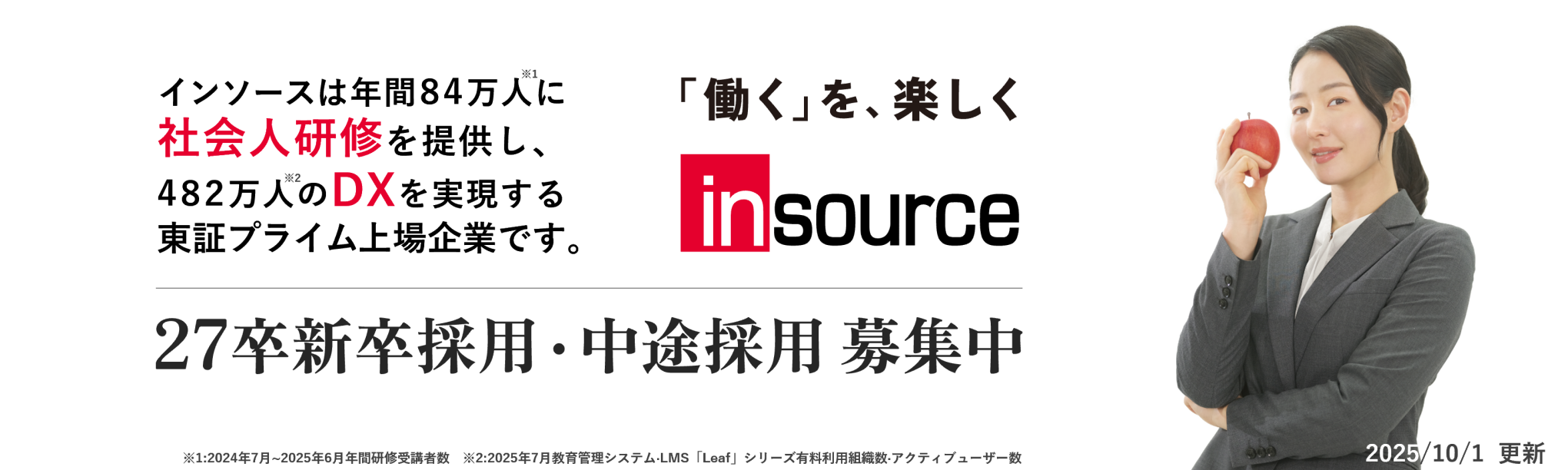






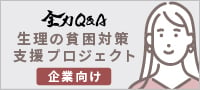
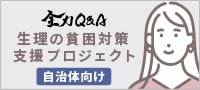




製造業のアナログ技術を活かした事例から学ぶ