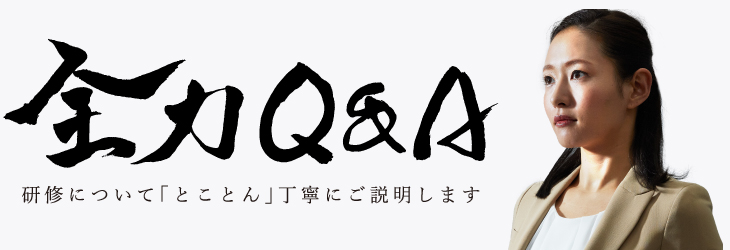2,755問の質問に全力でお答え!
評価者・考課者研修
お客さまから「評価者・考課者研修」に多く寄せられるご質問を掲載しております。
インソース社員が研修のプロとして丁寧に回答しておりますので、気になる点が少しでも解消されるよう、ご活用いただければ幸いです。
全て
- インソースの評価者・考課者研修のポイントはなんですか?
- 評価者・考課者研修と言ってもたくさんの種類があるようですが、どのように選んだらよいですか?
- 被評価者・考課者研修も実施したほうがよいのでしょうか?
- 当組織の現状にマッチするよう、プログラム内容は変更可能ですか?
- 当組織の評価・考課基準を踏まえた研修をご依頼できますか?
- 評価者・考課者研修ではどのようなケーススタディを行いますか?
- 当組織の状況を踏まえたケーススタディは作れますか?
- 被評価者・被考課者向けにおすすめの研修はありますか?
- 1時間の講演形式で研修はできますか?
- 研修後の受講者が取り組む宿題などはありますか?
- 自組織独自の目標設定シートを用いて演習をしたいのですが、対応はできますか?
- 業績評価がうまくできません。業績評価を強化する研修はありますか。
- 毎年評価者研修を1回2日間で実施していました。時間としては妥当でしょうか?長すぎでしょうか?
- 評価者・考課者研修とセットになるような、おすすめの研修はありますか?
- 評価者・考課者研修について、どのような要望がよせられることが多いですか?
- 評価者・考課者研修の受講対象者はどのような人でしょうか?
- 評価者・考課者と被評価者・被考課者の合同研修は、対応できますか?
- どんな人に講師をしていただけますか?
- 会場のレイアウトや、研修当日準備するものには何がありますか?
- 研修を実施するにあたって、受講人数は最低何人から最高何人までがよいでしょうか?
- 研修をご依頼するステップについて教えてください。また、事前に見学はできますか?
- 部下に嫌われることを恐れてついつい評価が甘くなりがちなのですが、どう対策したらよいですか?
- 評価者間で評定に差が出てしまい、被評価者の不満につながっているようです。何か解決方法はないでしょうか。
- 有効な目標管理の方法を教えてください。
- 評価面談の意義が感じられず、現場の管理職はあまり実施していないようです。何か対策はありますか。
- 期中のマネジメントとは何ですか?
- 評価・考課制度の運用が結構な手間なのですが、何か効率化するおすすめのサービスはございますか?
- 人事評価制度の構築について相談にのってもらえますか?
- 外国語対応は可能でしょうか?
- 評価・考課制度に関する映像教材(eラーニング)はありますか?
Q&A List
インソースの評価者・考課者研修のポイントはなんですか?
「制度の作り手」の論理に偏らず、「現場の活用側」からアプローチし開発した、教育プログラムを駆使し、貴組織の皆さまの人事評価の質を向上させることが可能です。ポイントは、評価・考課の意義は「人材育成と組織力向上」であることを理解いただくことです。 評価者・考課者研修と耳にすると、つい「評価・考課すること」に意識が向いてしまいますが、そもそもなぜ評価・考課するのか(しなければならないのか)という原点を改めて考え直していただきます。そして見つめた先に辿りつくのは「人材育成と組織力向上」です。 部下一人ひとりを育て上げることで組織力の向上につなげる。 そのためのツール(道具)が評価・考課であることをご理解いただき、そのうえで必要な考え方「目標管理」、「能力・考課評価」、「育成・日常指導」、「評価・考課面談」などをご要望に合わせて学んでいただきます。
評価者・考課者研修と言ってもたくさんの種類があるようですが、どのように選んだらよいですか?
受講者さまの役割、実施の時期・目的・ねらい等によっておすすめのプログラムは変わってまいります。 それらを営業担当者が伺ったうえで、最適なプログラムをご提案いたします。 よくいただくご要望とおすすめプログラムの例 ・評価全般について基本的な考え方とプロセスを確認したいなら 評価者研修~公正な評価のポイントを学び、納得感のある評価を行う ・評価のバラツキをなくしたいなら 評価者研修 ~評価基準ブラッシュアップ編(1日間) ・目標設定と面談力を学びたいなら (半日研修)実践!評価者研修~目標設定・面談編 ・期中の指導力をつけたいなら 評価者研修~期初面談と期中のマネジメント編(1日間)
被評価者・考課者研修も実施したほうがよいのでしょうか?
ぜひ実施をおすすめいたします。 被評価者は評価者以上に、評価・考課制度を「単なる給与・賞与を決めるための作業」としかとらえていないことが多くございます。 また、被評価者側は他者の評価シートを見る機会は多くないため、自分自身の目標設定や自己評価の書き方が正しいのかどうか確認するすべを持っていません。 その状態にある被評価者に対して、評価・効果の意義や評価シートの書き方を伝えることを「現場の評価者任せ」にしてしまうことは危険です。場合によっては評価制度にマイナスイメージを抱いてしまう被評価者も少なくないでしょう。組織全体として、評価・考課の意義や正しいプロセスに対する認識を統一していただくことは、評価・考課を人材育成につなげ、組織力を高めるために重要であるといえます。
当組織の現状にマッチするよう、プログラム内容は変更可能ですか?
可能でございます。 評価者・考課者研修を実施するにあたっては、必ず以下の3点を伺います。 ・貴組織の評価・考課の制度内容 ・制度の制定時期 ・制度の運用状況(現場に浸透しているか、形骸化していないか) 現状を伺ったうえで、研修で到達したいゴールを伺い、その実現に向けたプログラムをご提案いたします。
当組織の評価・考課基準を踏まえた研修をご依頼できますか?
可能でございます。 貴組織の評価・考課資料を可能な範囲でご提供いただくことで、貴組織に沿ったプログラムをご用意いたします。 また「テキストの中に自組織の資料を盛り込みたい」などのご要望にもお応えしております。
評価者・考課者研修ではどのようなケーススタディを行いますか?
「誰が見ても解釈にズレがない目標の設定ワーク」「評価者自身の考え方のクセに気づくワーク」「評価・考課を実際につけてみるワーク」「評価結果を部下に伝える面談ロールプレイング」等を実施いたします。 特に「評価・考課を実際につけてみるワーク」「評価結果を部下に伝える面談ロールプレイング」については、受講者さまが考えやすく違和感を感じないようなケース設定にするため、カスタマイズを行うことが多くございます。 一例をご紹介します。 「自分の意見を譲らず、組織の決定に従わない部下への評価(考課)・フィードバック」 「意欲・やる気はあるが仕事が遅い部下への評価(考課)・フィードバック」 これらは評価者・考課者が評価・考課を行う際に、誰もが一度は頭を悩ませ、つまずきがちな場面といえます。 このような部下に対する評価・考課をどのようにつけたらいいかという悩みと、またそれを本人にどのように伝えたらいいかを考えていただきます。 そして周囲とのグループワークを通じて考え、意見を共有し、更には評価者・考課者役と被評価者・被考課者役とに分かれてロールプレイングをすることで、研修で学んだ内容を現場で活かせるレベルまで引き上げ、自分のものとすることが可能になります。
当組織の状況を踏まえたケーススタディは作れますか?
可能でございます。同業界にて実施した実績をもとに、当社側からお客さまの課題に沿っているであろうケース案をご提示することもできますし、受講者が頭を悩ませがちな状況や人事ご担当者さまが想定されている課題をご教示いただくことで、貴組織オリジナルのケーススタディをゼロから作成することも承ります。 なお、ケーススタディの作成にあたっては、受講される方々にあらかじめ事前課題を実施することが可能です。 「評価・考課において困っていることはありますか?」などのアンケートに答えていただくことで、受講者の抱える悩みや課題を具体的にくみとり、ケーススタディやテキストの作成に反映することができるようになります。 研修効果を高める 事前課題
被評価者・被考課者向けにおすすめの研修はありますか?
はい、ございます。 被評価者に求められることは主に3つございます。 ①評価・考課制度を理解していること ②自分の目標がきちんと立てられること ③自己評価・考課がきちんとできること 上記を含めたお客さま要望に合わせて、ご提案いたします。 被評価者研修 ~目標設定編(半日間) 被評価者研修 来期へつなげる振り返り編(半日間)
1時間の講演形式で研修はできますか?
可能ではございますが、おすすめはいたしかねます。 1時間という限られた時間での研修は、講義メインで進行せざるを得ず、講義だけになる場合、ケーススタディなどを通じて実際に考えていただくことが難しく、研修効果は薄まります。 もし短時間や講演形式での研修ご要望の場合は、そのようにご検討されている背景などをまずはお話しください。 伺った内容をもとに、限られた時間の中で最適なプログラムとをご提案いたします。
研修後の受講者が取り組む宿題などはありますか?
評価者・考課者研修の場合、宿題をご用意することはあまり多くはありません。しかし、評価のプロセスの中でも「期中のマネジメント」をメインにしたプログラムの場合は、最後に、翌日から3カ月かけて取り組む「アクションプラン」を作成いただき、その実施をお願いすることがございます。「部下の行動記録をつける」「月1回部下と面談の時間を設ける」など、部下とのコミュニケーションのとり方に関するアクションを設定される方が多いです。 アクションプランの実施状況の確認は基本的にはお客さまにてお願いしておりますが、弊社にて確認とリマインドを行う「呼び覚まシステム」というサービスもございます。月に1回3カ月間、WEB上のアンケートを弊社から受講者さまに直接お送りし、研修内容が身についているか、実践できているかを確認させていただくプラスアルファのサービスでございます。 研修効果を高める「研修呼び覚まシステム」
自組織独自の目標設定シートを用いて演習をしたいのですが、対応はできますか?
対応可能です。多くの実績がございますのでご安心ください。 日頃、実際に使用されている評価シートを元に、貴組織オリジナルの演習を作成いたします。
業績評価がうまくできません。業績評価を強化する研修はありますか。
はい、ございます。 業績評価がうまくできない原因は、「目標が高すぎる・低すぎる」、「目標が数値化されておらずあいまい」など、評価のプロセスでなく目標設定のプロセスに原因があることが多いため、以下の研修がおすすめです。 目標管理研修
毎年評価者研修を1回2日間で実施していました。時間としては妥当でしょうか?長すぎでしょうか?
適切であると考えます。 研修において評価のスキルを向上させるには、とにかく評価のすりあわせと面談を何回も実施することです。特に面談のロールプレイングは1人最低3回は実施いただくことを推奨しています。 1日目に評価の意義や目標管理の全容を理解し、2日目にひたすら実践を行うような研修が、特に自治体のみなさまには人気です。 評価者研修~評価者としての総合スキル習得編(2日間)
評価者・考課者研修とセットになるような、おすすめの研修はありますか?
はい、ございます。 評価・考課の内容に加え、ご要望に応じて「部下との面談力向上」や「部下とのコミュニケーション実践」など、期中のマネジメント力を高める内容のものがおすすめです。当社のHRコンサルタントにご相談、またはお問い合わせください。 おすすめのプログラム例 コーチング研修~部下の目標達成を支援する編(1日間) 部下の成果の上げ方研修~成長を促し、組織貢献へとつなげる(1日間)
評価者・考課者研修について、どのような要望がよせられることが多いですか?
【評価の意義と目的】 ・人事評価制度のルール・意義・目的を理解してほしい ・社員に火をつけると同時に環境を整えてほしい(扱いやすいルールとツールでなければ途端に足はとまる) ・被評価者は評価に備えてほしい(準備なしに評価時期をむかえ、初めて見るシートと格闘しても自身をうまくプロデュースできない) 【目標管理】 ・自身の役割をきちんと認識してほしい(階層別研修も必要) ・目標の設定と書き方を学びたい(職種に関係なく設定できるようになってほしい) ・目標の中身が縦と横で連鎖してほしい(課題設定力・シナリオ構築力が必要) 【日常指導】 ・部下の成長を支援する育成支援力を身につけたい ・日常指導こそ、納得度が高く未来へ繋がる評価を実現させる術であることを知ってほしい (日常指導なく評価で打ち明ける「不意打ち」は部下の気持ちを一瞬で冷ます) 【フェアな評価】 ・感覚的判断、主観やつじつま合わせではない、フェアな評価をしてほしい ・部下の高い自己評価にも対応できる ・自身の過大・過小評価をしない 【評価面談】 ・面談により前向きにさせる面談指導力を得てほしい ※訓練が重要なので研修では面談を最低5回は繰り返す ・下位(良くない)評価も上手に伝えてほしい
評価者・考課者研修の受講対象者はどのような人でしょうか?
評価者・考課者向け、被評価者・考課者向けともご用意がございますのであらゆる方にご受講いただけます。ただしご要望が多いのは、新任管理職など新たに評価する立場になった方向けです。もしくは、評価制度を新たに導入もしくは改訂された際に、新制度浸透のための周知もかねて、管理職全員に対して実施されるお客さまもいらっしゃいます。
評価者・考課者と被評価者・被考課者の合同研修は、対応できますか?
可能ではございますが、おすすめはいたしかねます。理由は、2つあります。 ひとつは、評価者・考課者の前で被評価者・被考課者の受講者が忌憚のない意見交換ができなくなってしまうことです。実際に合同研修は実施しておりますが、被評価者・被考課者が遠慮をしてしまい、本心の意見が言えないなどの理由で、研修効果が薄れます。 ふたつめは、合同で行う場合には被評価者・被考課者目線で進めることになるためです。そのため、評価者・考課者が本来学びたいことが習得しにくくなるという点で、研修効果が薄れてしまいます。
どんな人に講師をしていただけますか?
評価者・考課者研修の場合は、内容によって以下のいずれかの講師を営業担当が選定し、おすすめいたしいます。 ①評価・考課制度に関する知識が豊富な「人事の経験が長い講師」 ②(評価者・考課者対象の場合)受講者さまの現場でのお悩みを自身も経験したことのある「管理職としての現場経験が長い講師」 新任管理職でなくすでに管理職経験の長い方が受講対象者の場合は、②がおすすめです。 また、受講者さまを動機づけ、学んだ知識を実践できるよう導くうえで、受講者と講師の「相性」は非常に重要であると考えております。 できる限り、お客さまの業界や受講者さまの職種について理解の深い講師を選定しますが、そのほかにもご要望(一人ひとりに寄り添う姿勢で親しみを感じさせるタイプ、適切な距離を保ち厳しく指導するタイプ、冷静・ロジカルに話すタイプ、熱く語りかけるタイプなど)がございましたら、ぜひお聞かせください。 インソースの講師の特徴
会場のレイアウトや、研修当日準備するものには何がありますか?
研修会場のレイアウトは、4~6名1組のグループを受講者の人数に応じて構成する「島型」を推奨しております。グループディスカッションを行い他者の意見を聴くことで、内容の理解を深め、アウトプットの質を高められるからです。受講者人数が40名を超える場合は「教室型」で実施することもございますが、ワーク比率は研修時間の半分未満、形式は隣同士のペアワークが中心になります。 インソースの研修スタイル 評価者・考課者研修の場合は、準備いただくものは以下のとおりです。プロジェクターやスクリーンは使用いたしません。 ・人数分のテキスト、アンケート、付随資料(インソースから納品した資料やお客さまのガイドラインなど) ・講師用マイク1本 ・講師用ホワイトボード2枚、マーカー(なるべく3色程度) その他ご不明点などございましたら、事前に営業担当者へお気軽にご相談ください。
研修を実施するにあたって、受講人数は最低何人から最高何人までがよいでしょうか?
原則としては、講師1人あたり20~30名程度でお願いしております。また、受講者数が20名に満たない場合でも、1名さまから講師派遣型で実施はできますが、研修効果・費用対効果を鑑みますと、少人数の場合は弊社公開講座もおすすめです。ご希望の日時で公開講座の開催予定がない場合でも、貴社内で4名さま以上お集まりいだけましたら、 ご希望の日程で公開講座を開催することも可能です。 ※ご希望の日程で公開講座を開催する場合、他社の受講者さまも参加される可能性があることをあらかじめご了承ください 4名以上受講者さまがいれば、ご希望の日程で公開講座を開催! 研修リクエスト 評価者・考課者研修に関連する公開講座の一覧
研修をご依頼するステップについて教えてください。また、事前に見学はできますか?
お問い合わせをいただきましたら、おもに以下のステップで進めてまいります。 ①弊社の営業担当によるヒアリング 日程や場所などの情報に加えて、評価者・考課者研修を検討されている背景や、研修によって達成したい目的をお伺いします。併せて、これだけは伝えたいというトップからのメッセージや、弊社ホームページで気になっているプログラムなどがございましたら、ぜひご教示ください。 ②ご提案 ヒアリング内容をもとに、お客さまに最適なプログラムをご提案いたします。 (③ご希望があれば公開講座のご見学) 研修内容や講師の様子を実際に見学したい、というお客さまには、全国各地で通年実施している公開講座を無料でご見学いただけます。ご判断の材料としていただければ幸いです。 ※ご提案している講師に公開講座登壇の予定がない場合は、研修内容のみのご確認となりますことをあらかじめご了承ください ④実施前打ち合わせ・事前課題の実施 研修の進め方や事務面での準備状況の確認など、1~3回程度お打合せを行い、研修効果が最大になるように準備を行います。並行して受講者さまに対してアンケート形式の事前課題(2問程度)を実施することも可能です。 ロールプレイングテーマの作成や受講者さまのお悩みを踏まえた講師の経験談の準備に活用し、研修効果を高めます。 ⑤研修資料納品 お打合せ内容を踏まえたテキストを弊社のクリエイターが作成し、準備物の確認書類と合わせてデータで納品いたします。お客さまにて受講者数分の印刷をお願いいたします。 ※テキストの印刷を弊社にて承ることも可能でございます。 ⑥研修実施 ⑦アンケート結果のご報告 研修当日、受講者さまに簡単なアンケートへのご協力をお願いしております。結果は弊社にて集計し、ご担当者さまにご報告いたします。 インソースの研修の流れ
部下に嫌われることを恐れてついつい評価が甘くなりがちなのですが、どう対策したらよいですか?
日々ともに努力しているかわいい部下に、何とかして良い評価をつけてあげたいと思う気持ちは、ある種自然なことです。ただ、根拠がなく良い評価をしても二次評価で差し戻されてしまいます。 しっかりとした根拠を自分自身でもつためには、期中の部下の行動をしっかりとみておかなければなりません。面談を効果的にするという観点からも、「期中の部下の観察」は重要です。特に悪い評点をつけなければならない場合、その根拠をしっかりと部下に伝え、納得させる必要があります。次の期に部下に良い評価をつけるためには、どういう点が課題なのか、何をすれば悪い部分が解消され、良い成果、パフォーマンスとなるのか。これも部下の期中の行動をきちんとみておかなければ良いアドバイスができません。 目標管理もそうです。期中に部下をしっかり観察し、適正なフィードバックを与えることで、期末の目標達成へとつながります。そうした意味で、評価の「肝」とは「部下の期中の観察」、これがすべての根幹だと考えます。 コラム:奈良時代の評価制度
評価者間で評定に差が出てしまい、被評価者の不満につながっているようです。何か解決方法はないでしょうか。
能力評価における評価者の課題は、評価者間における評価のレベル感のズレ(評価の甘辛)の問題に尽きると思います。これは業種、業界を問わず、永遠の課題で、完全な解消は不可能な課題です。 ただし、例えば5段階評価として、その真ん中の標準評価「3」に当たる行動・成果について、評価者間で妥当な落としどころ(適正なレベル)を議論し、共有することで、評価者間の甘辛の是正は一定程度可能です。 評価の改善に熱心な会社では、評価の後、管理職を2泊3日ぐらいでホテルに缶詰めにし、部下につけた評価の根拠を発表させ、それを基に議論をする「すりあわせ会議」を行っているところもございます。インソースが運営する、翌日からの仕事を楽しくするアイデアに出会えるサイト「gambatte研修担当者」でも、その方法をご紹介しております。 すぐできる!カンタン研修レシピ「1時間で評価の甘辛を良い塩梅にするワーク」
有効な目標管理の方法を教えてください。
目標管理についてよく伺う一般的な課題と、インソースの考える原因と対策は以下のとおりです。 ①目標が形骸化するという課題 まず、上司と部下で期初にしっかりと相談して妥当なレベル感の目標が立てられていないことが考えられます。上司と部下で一緒に目標を立てれば、両者とも目標に対して、親近感、責任感が芽生え、実行しよう、達成しようという意識が醸成されます。 ②目標設定が低すぎるという課題 目標の設定レベルを、ルーティンワークや、普通にやっていてもできるものではなく、「1~2割増し」くらいのレベル感・成果のものにするのが適当だと考えます(少し頑張れば達成できるレベル)。 ③目標があいまいで検証できないという課題 目標を具体的に、できれば数値を使った定量的なものにし、誰でも再検証できるものにすることによって解消が可能です。 ④管理部門など非営業部門の目標設定が難しいという課題 どの組織にも共通する、永遠の課題ですが、定量化が難しい場合でも、理想の姿と現状のギャップを埋めるという視点で目標設定を行うのが王道です。例えば、「業務の効率化」というあいまいな目標ではなく、「〇〇の作成が現状1件15分かかっている」という現状の課題に対し、「1件10分が理想」というあるべき姿を達成するために、「5分の時間短縮」を定量的な目標とし、そのために行う具体的な行動を考えるというようにすれば、非営業部門でも、誰でも再検証できる目標設定が可能です。
評価面談の意義が感じられず、現場の管理職はあまり実施していないようです。何か対策はありますか。
面談に関する課題としては、以下の3つが代表的なものです。 ①納得感ある評価の伝え方ができない(評価の根拠が不明確) ②特に下位評価の場合に次につながるフィードバックができない ③日常的な指導がなく評価の場で初めて悪い所や課題を指摘する (「不意打ち」) これらを解消するためには、「期中の部下の観察」をしっかりと行うことが重要です。観察をしっかりと行っていれば、①自ずと納得感のある評点の説明ができますし、②次にどうすれば良いかの適切なアドバイスもできます。③普段から部下とコミュニケーションがとれていれば(部下が「上司は自分の事をよく見てくれている」と感じていれば)不意打ちは生じません。
期中のマネジメントとは何ですか?
部下の成長を支援するための評価期間中(日常)の指導育成や面談を指します。 日常の指導があるからこそ、部下が日々成長し、お互いに納得のいく評価も可能となります。逆に日常指導なく評価で打ち明ける「不意打ち」は部下のモチベーションを一瞬で下げる恐れがありますので注意が必要です。 評価者研修 期中のマネジメント編(1日間) 部下との面談力向上研修(1日間)
評価・考課制度の運用が結構な手間なのですが、何か効率化するおすすめのサービスはございますか?
はい、ございます。 今使っている評価シートをそのままWEB化できる「人事評価シート WEB化サービス」が人気です。 ・紙やExcelなので運用が大変 ・みんなの提出が遅くて大変 ・人事評価は教育と連動させたいと思っている といったお悩みに対して是非ご検討いただければと思います。 人事評価シートWEB化サービス 評価シートのWEB化サービス以外にも様々なご支援ができます。お気軽にお問合せください。 人事制度設計支援サービス
人事評価制度の構築について相談にのってもらえますか?
可能でございます。 制度を新しく導入したい、あるいは刷新したいなど、ご要望は多岐に渡っております。育成のための評価制度であるためには、制度が公正公平であることと、運用する当事者の意識を高める必要があります。お打合せに参りますので、まずは営業担当者までご連絡ください。 人事制度設計支援サービス 教育体系に関する無料セミナー
外国語対応は可能でしょうか?
可能です。 (グローバル企業向け)評価者研修(半日間)
評価・考課制度に関する映像教材(eラーニング)はありますか?
ございます。 インソースは映像制作も得意としております。パッケージ製品の他、ご要望に応じたカスタマイズも可能です。 eラーニング 人事評価・人事考課講座 eラーニング ケース映像で学ぶ評価面談講座 eラーニングについては、パッケージ製品に加えてカスタマイズeラーニング制作、eラーニング視聴のためのインフラ提供など、お客さまのお悩みに応じた多様なソリューションをご提供しております。ぜひお気軽にご相談ください。 人事サポートシステム「Leaf」をインフラとした動画教育 動画教材(eラーニング)について
- 本サービスはGPTsにて作成しております
- 別途ChatGPTの有料プランアカウントが必要となります