新着
-

-
ダイバーシティ
-
2025/01/24
生理って何がおこっているの?(生理の貧困対策支援PJ)
「生理」について多くの方に知ってただきたく、「生理とは何か?」についてお話いたします。この記事を読んで、男女問わず生理についての理解を深めていただけますと幸いです。
-
ダイバーシティ
-
-

-
調査
-
2024/12/20
社会人として身につけたい常識力について~アンケート調査の結果より
近年、転職などの増加により、新人だけではなく中堅や管理職に至るまでOJTなどでは教えない部分の知識、経験不足が課題であると伺う機会が増えました。そのような背景のもと、明文化しづらい「常識力」というテーマでアンケート調査を実施し、これだけは社会人として身につけてほしいという「常識」をお尋ねしました。2024年10月に企業・組織の人事・教育担当者向け実施したアンケート調査の結果から一部抜粋してご紹介いたします。
-
調査
-
-

-
ダイバーシティ
-
2024/12/11
インソースのSDGs ~障がい者福祉団体支援プロジェクト~
障がいのある方が製造した商品を集めたECサイト「mon champ(モンシャン)」は、フランス語で「私の畑」という意味です。畑には野菜や果物、花など色とりどりの世界が広がっているように、mon champでも様々な視点から心を込めた素敵な商品を取り揃えてお届けします。
-
ダイバーシティ
-
-
-
経営者
-
2024/11/22
インソース流健康経営~健診結果管理システムについて
健康経営に力を入れている企業は、社会的にも評価され、投資家や取引先からの信頼も得ています。そんな中で、従業員の健康管理を効率よく進めるためのツールとして「健診結果管理システム」が注目されています。
-
another
-
-
-
経営者
-
2024/11/22
インソース流健康経営~喫煙防止の3ステップ
健康経営とは、企業が従業員の健康を経営課題と捉え、健康促進活動を行うことで、従業員の健康と企業の生産性向上を両立させる経営手法です。その中で、喫煙防止は重要なテーマの一つとなっています。インソースでは、健康の重点課題として「生活習慣病(運動習慣・喫煙対策)」を定めています。全従業員の喫煙対策をできるだけ早期に実現するために、以下の3ステップで取り組むこととしました。
-
another
-
-

-
偉人に学ぶ
-
2024/10/25
《最終回》岩崎小彌太に浸る7日間vol.7「小彌太と財閥解体」
三菱重工業株式会社の誕生に尽力した岩崎小彌太。小彌太は頭脳明晰で、頑固で強引な所はあるが、組織全員の力を活用して厳しい時代の中でも三菱を成長させた人です。今回はそんな岩崎小彌太がどのようにして三菱ををさせたのかを彼の人生を辿りながら紐解いていきます。
-
偉人に学ぶ
-
記事一覧
-

-
管理職
管理職として成果を上げるために~管理職と社外取締役の座談会 後編
会社組織の中で成果や利益を出していくうえで必要なこととは何でしょうか。現在インソースで管理職として活躍中の3人が感じている課題について、社外取締役との意見交換を行いました。 前編はこちらから 管理職として成果を上げるために~管理職と社外取...
-
管理職とは
-
-

-
管理職
管理職として成果を上げるために~管理職と社外取締役の座談会 前編
会社組織の中で成果や利益を出していくうえで必要なこととは何でしょうか。現在インソースで管理職として活躍中の3人が感じている課題について、社外取締役との意見交換を行いました。 【座談会参加メンバー】 藤岡(社外取締役) M...
-
管理職とは
-
-

-
管理職
令和流の営業マネジメントの「要」とは~"個を見る"部下育成で最大の成果を出す
本コラムでは、インソースの営業部門を統括するマネージャーが実践する、"個を見る"部下育成で成果を出す3つの手法をお伝えします。一昔前の「売上(数字)至上主義」から脱却し、多様な価値観を持つイマドキ世代の部下たちをどのように導けば売上目標を達成することができるのか、参考にしていただければ幸いです。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
突然の社長命令、あなたはその真意をくみ取れるか(後編)
これってまさか左遷辞令!?本コラムでは、弊社のエグゼクティブ・アドバイザーが、「社長からの突然の異動辞令の真意が分からない」と悩む管理職の方に、社長の頭の中にある2つのキーワードから、辞令の裏に込められた真意は何かを解き明かします。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
突然の社長命令、あなたはその真意をくみ取れるか(前編)
これってまさか左遷辞令!?本コラムでは、社長をはじめとする経営層とのコミュニケーション不全に悩む管理職の方に、経営層との意思疎通がもっと上手くいくよう、弊社のエグゼクティブ・アドバイザーが経営層の2つの"思考のモノサシ"を解き明かします。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
「次世代リーダー育成」の時流とメソッド
本コラムでは、次世代リーダー育成の対象層が若年化しており、どのような人材が求められているかについてご紹介します。次世代リーダーの「経験不足」「視座の低さ」「エンゲージメントの低さ」といったよくある課題にもお答えしています。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
管理職の"自信喪失"を克服する方法
本コラムでは、弊社のエグゼクティブ・アドバイザーによる「管理職の"自信喪失"を克服する方法」をご紹介します。リーダー失格では?という不安に駆られ、メンタルヘルス不調をきたす前に、自らを立て直すための処方箋として役立てていただければ幸いです。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
"お荷物部下"を大活躍させる管理職の秘策とは
本コラムでは、弊社のエグゼクティブ・アドバイザーによる「貴組織の"お荷物部下"を大活躍させ、最強のチームをつくるための秘策」をご紹介します。能力的にバラツキが大きいメンバーを抱える管理職がチームの成果を出すための参考としていただければ幸いです。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
最強チームは風通しも良く、ハラスメントとも無縁
本コラムでは最強チーム構築に必要な考え方について弊社のエグゼクティブ・アドバイザーがお伝えします。「目的」重視の思考と、「求められる人材像」の定義。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
全社員向けDX教育の実施は待ったなし
目次 第4...
-
管理職とは
-
-

-
管理職
上司は新入社員に一生もののアドバイスを
新入社員が成長し活躍し、長きに亘って会社に貢献するために、上司からのアドバイスはかかせません。本コラムでは、ぜひ新入社員の方に語っていただきたい内容を記載しています。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
部下の目標管理を上手に行うための5つのポイント
本コラムでは、管理職として部下の目標管理を上手に行うための5つのポイントをご紹介します。目標管理とノルマ管理の違いや、目標設定から達成させるまでの流れなど、参考にしていただければ幸いです。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
「"攻め"にも"守り"にも強いリーダー」になるための4つの課題
本コラムでは昇進された新任管理職の方に、弊社のエグゼクティブ・アドバイザーが「"攻め"にも"守り"にも強いリーダー」になるための4つの課題をを明らかにします。管理職に昇進した以上、大いに活躍してさらに上を目指すために、自分を磨く計画の参考となれば幸いです。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
新任管理職へ贈る4つの言葉~イチ担当者からの"大転換"を遂げるために
本コラムでは昇進された新任管理職の方に、弊社のエグゼクティブ・アドバイザーからの「新任管理職へ贈る4つの言葉」をご紹介します。イチ担当者から管理職への大転換という壁を、難なく乗り越えていただくための一助となれば幸いです。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
管理職が知っておくべき、仕事の配分
本コラムでは、管理職の役割の一つである仕事の配分についてご紹介します。新人やアルバイト社員など業務に不慣れな非熟練者に回せる業務は全体の何割を占めるのか、また彼らのパフォーマンスを引き上げるにはどうすればよいのか、参考にしていただければ幸いです。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
人的資本経営への取組み~PTの設置と活用
今なぜ、「人的資本経営」が脚光を浴びるのでしょうか。その答えは、企業社会が、時代の転換期を迎えているからです。それでは、「人的資本経営」をどのように進めれば良いのでしょうか。その基礎となる人的資本価値をどのように高めれば良いのでしょうか。その方法について、ご紹介いたします。
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
人材戦略の進め方~逆算思考を活用する
人事部の方から「人材戦略をどのように進めれば良いでしょうか」と質問を受けることがあります。しかし、人材戦略のみに焦点を当て、これを独立したテーマとして論じることが果たして有効と言えるでしょうか。企画部と人事部が一体となって「人材戦略は事業戦略(経営環境の変化)に従う」を実践することが会社の発展には必要不可欠です。事業戦略の内容によって人材戦略がどのように決まるのか、この記事でご紹介いたします。
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
【管理のツボ公開(Ⅳ.リスク管理編)】リスク管理のツボ~リスクは必ず表面化する
全4回シリーズで管理のツボについて綴ります。今回は「Ⅳ.リスク管理編」です。前回の記事を踏まえて、リスクを認識する方法についての見解を語ります。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
【管理のツボ公開(Ⅲ.PDCA編)】PDCAしっかりと回し、成果を上げるツボ
全4回シリーズで管理のツボについて綴ります。今回は「Ⅲ.PDCA編」です。前回の記事を踏まえて、PDCAしっかりと回し、成果を上げる方法についての見解を語ります。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
【管理のツボ公開(Ⅱ.人材育成編)】人材育成のツボを押さえて、効果的に自分を育て、部下を育てる
全4回シリーズで管理のツボについて綴ります。今回は「Ⅱ.人材育成編」です。前回の記事を踏まえて、人材育成のツボについての見解を語ります。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
【管理のツボ公開(Ⅰ.自己採点編)】できる管理者は"ツボ"を押さえている~4つの質問に答えてあなたの管理力を確認しよう
できる管理者になりたい。このために、どのように自分自身を磨けば良いのか。これは管理者に共通する最重要課題の一つです。実は、できる管理者になるための方法は、案外、簡単なところにあります。この記事では、その方法についての見解を語ります。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
新たな戦略的視点~"分散型社会・経済"の効用
新たな戦略視点として「"分散型社会・経済"の効用」を取り入れてはどうでしょうか。これによって、今、経営課題として急浮上している"ESG"や"SDGs"への取組みが自ずと促進されます。この点を以下に分かり易くご説明いたします。
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
悪い情報があがってこないのはリーダーの責任~「風通しの良い組織」作りに向けて
良い情報は言わなくても上がって来る。他方で、悪い情報は言っても上がって来ない。これは、リーダーが抱える代表的な悩みの1つです。組織において、そもそも悪い情報を認識する力は、総じて低くなる傾向があります。この記事では、真の「風通しの良い組織」をどのように作れば良いのか、について見解を語ります。
-
部下育成
-
-

-
管理職
「なぜコーチングが上手くいかないのか?」95%以上のリーダーが答えられない質問
「部下の育成に『コーチング』を取り入れたが、部下が思うように育たない」「若い部下には『ティーチング』を実施しているが、効果がなかなか出てこない」このような嘆きのご相談を数多くいただきます。部下全員の活躍は、リーダーにとっての悲願です。一体どこに問題があるのでしょうか。
-
部下育成
-
-

-
管理職
ビジネス格言「会社経営に最適解なし」
会社経営において "最適化" "最大化" "最小化" を実現することはできません。誰もがベストだと信じて選択した案であっても、実施してみると途中で数々の修正を迫られるものです。そのため実際の会社では、 "最適化" "最大化" "最小化" を念頭に置きつつも、これに代わる合理的(=「最適」に対して用いられる言葉)な手法が活用されています。この記事では合理的な手法、意思決定のために覚えておきたい基準についてご紹介いたします。
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
ビジネス格言「"健全な危機感"が優れた創意を生む」
健全な危機感が優れた創意を生む――ビジネスの現場では良く耳にする言葉です。状況を正しく把握したうえで覚える健全な不安感・危機感は、確かに変革・改善のための重要な第一歩となります。「如何にして健全な不安感や危機感を覚えるか」そして「これを出発点にして如何にして優れた創意を生み出し、真の改善に結びつけるか」について、見解を語ります。
-
業務管理
-
-

-
管理職
今、目的・目標意識の持ち方は「二刀流」の時代へ
出来る人と出来ない人を分ける重要な要素の一つに、「本人に目的・目標意識が備わっているかどうか」があります。しかし、これだけで十分と言えるのでしょうか。求められるのは「二刀流」です。二つ目の目的・目標意識を持つための方法をご紹介いたします。
-
業務管理
-
-

-
管理職
ビジネス格言「情報の取得は"外"、その深化は"内"」
ビジネス格言の一つに、「情報の取得は "外"、その深化は "内"」というものがあります。しかし、この格言にピンとくる方はごく少数で、多くの方は意味がよく分からないのではないでしょうか。以下にこの主旨を説明しましょう。是非、ご自身の思考・行動指針としてご活用ください。
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
新任役員研修の狙いを問う。管理職教育の延長ではない
上場会社の大宗を占める3月末決算会社の定時株主総会が開催され、今年も、数多くの新任役員が誕生しています。良い船出が出来るようにと、会社は、彼らに新任役員研修の受講を推奨します。この記事では新任役員研修の狙いについての見解を語ります。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
たかがリスク、されどリスク。リスク管理の重要性を再確認しよう
「悪いことは起きない」「このままでは不味いが、当面大丈夫」日本人は総じてリスクに対して楽観的と言われています。これは、戦後、危機やリスクに対してどう向き合うかの教育を敢えて避けて来た結果である、と指摘する人もいます。この記事ではリスク管理の重要性についての見解を語ります。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
初任管理者研修の「3種の神器」、1つ欠落していませんか?
初任管理者研修と言えば、「人事評価」と「労務管理」の2つが定番です。管理者は、部下の評価・処遇や残業・有給休暇取得などの問題に適切に対処しなければならないからです。しかし、研修は以上の2つで十分でしょうか。
-
管理職とは
-
-

-
管理職
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の事業戦略・人事戦略を考える ~「特徴的な4つの事象」「出現しはじめた有力分野」
新型コロナウイルスによる人命や経済への大打撃は、消費者・国・企業がこれまで活用してきた考え方や行動指針を一変させてしまいました。今後、何が起きるのか。今回は特徴的な事象を4点取り上げながら、企業経営に示唆するところを述べてまいります。
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
「イマドキ世代」の育成にあたる管理職が注意すべきこと
最近の新人・若手の傾向には、行儀がよく真面目だと肯定的に評価する声がある一方で、彼ら・彼女らの受け身な姿勢に物足りなさを感じている声も聞かれます。このイマドキ世代は「シックスポケット」世代と呼ばれていて、管理職世代とは異なる環境で生まれ育ってきました。管理職がイマドキ世代を主体性のある部下に育成するには、彼ら・彼女らの特性を理解し受け止め、一人ひとりを組織ぐるみで面倒を見る丁寧なOJTが効果的です。
-
部下育成
-
-

-
管理職
管理職に必要な「ロジカルシンキング」とは?①
誰でも管理職になってから最初に苦労することのひとつは、部下に何か話す時、「話が分かりません」と言われることです。たとえば仕事の仕方を指示したら、「係長の話の内容がよくつかめない」とか「課長が何を言わんとしているのか理解できない」と返された場合などです。管理職の立場は、「リーダー」となって、部下を管理し仕事を常に見直し、業務を引き継ぐ後継者を育て上げる立場です。部下に分かりやすく話すには、どうしたらいいのでしょうか? その一つの方法は、「つじつまが合っている」という話し方、つまり論理的に話すということです。管理職にこそ、この「ロジカルシンキング」(論理思考)が必要です。
-
部下育成
-
-

-
管理職
IT導入で変化する"係長"の仕事
技術革新やグローバリゼーション、金融化(finanicialization)のトレンドが容赦なく襲う時代に、さらにIT導入という変化が組織を大きく変えつつあります。係長の仕事も、かつての「日本的経営」のブルーカラー中心の形から変わりました。係長を悩ます「雑務」や「調整業務」というわずらわしさが、昔以上に問題になっています。中間管理職の基本的能力(概念化能力、実務遂行能力、対人関係能力)を持つ「新しい係長職」を育てることが、組織改革のキーポイントになってきています。
-
業務管理
-
-

-
管理職
女性管理職を増やすファーストステップは?
近年では働き続けたいという女性は増加し、企業の人材確保や多様化の観点や、政府や自治体の行政的な取り組みなどを背景として、女性管理職の育成が求められています。しかしながら、出産などのライフイベントを機に離職する女性が依然多く、日本の女性管理職の男性に対する割合は未だ低いのが現状です。 女性の雇用を促進し、女性管理職を育成するため、「日本版ダイバーシティ・マネジメント」の一つとして、職場でも「男性社員に対する女性社員の数の割合が多いチーム」を増やすことを提言します。
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
組織の問題を3つの視点で解決
管理職の犯す判断ミスは、被害が組織全体に拡大して、企業経営にまで大きなダメージを与える場合があります。管理職が、自分たちで解決できない問題を組織内に抱え込んでしまい、上部に提案も報告も十分しないというのはもっとも困ったことです。問題を解決するためには、まず組織内の風通しを良くし、情報交換や情報共有を十分になさなくてはなりません。そのためには、問題を見る三つの視点をしっかりと据えて、解決方法を考えることが大切です。
-
業務管理
-
-

-
管理職
「組織のフラット化」は若手の自律を促せるか?
日本は外国に例を見ないほど少子高齢化社会が進んでいます。また新興国の成長による「全世界のフラット化」、世界中が実質的に1つの市場となる「グローバル化」など経済環境の激変も見られます。そんな現代の社員には、環境に適応して、自ら経営判断を下し、素早く実行に移すという担当者の「自律性」が求められています。昨今導入された「組織のフラット化」は、実は中間管理職の排除に終わらず、「若手社員の自律性向上」と「各組織力の強化」を目指すという見直しがなされ始めています。
-
経営者の視点
-
-
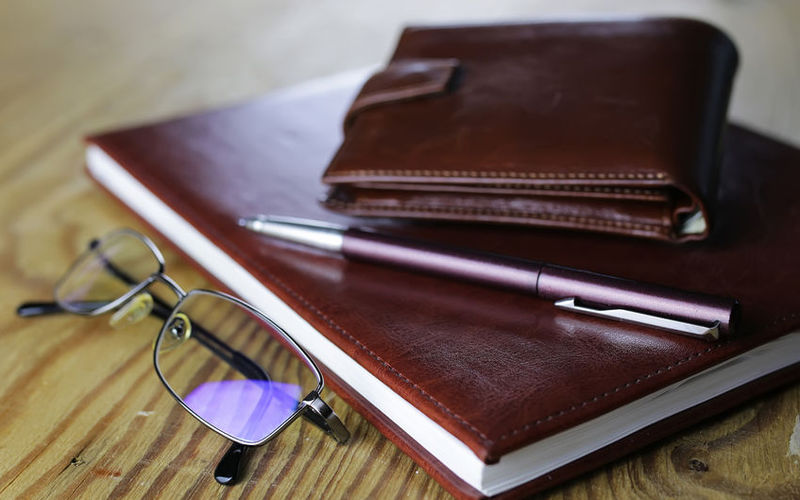
-
管理職
「仕事を任せる」と「仕事を丸投げする」の違い
権限委譲が上手にできることは、管理職に求められる基本的なスキルです。しかし、ややもすると権限委譲が、単なる丸投げになってしまうことが多いように思われます。丸投げは業務の品質や効率を劣化させたり、大きなリスクをはらむ場合もあります。丸投げの弊害と原因を知って、丸投げを回避し、権限委譲を正しく行うことが重要です。管理職が部下に仕事の丸投げをした場合、自覚症状がないこともあります。「何が丸投げなのか」「どこが丸投げなのか」、そのポイント3点をまず理解しましょう。
-
部下育成
-
-

-
管理職
ゼネラリストとスペシャリスト
ビジネスにおいてエッジの立った誰にも負けないスキルを持つことはとても重要です。技術革新の進む現代、専門分野にとらわれずに「管理や経営」に対してのスキル向上にも精力的に取り組む社員が求められています。つまりゼネラリストでありスペシャリストでもある、マネジメントの出来るスペシャリストは貴重な人財です。これからの時代は、 「ゼネラリスト」と「スペシャリスト」のどちらが有利かではなく、どちらもプロフェッショナルであるという点で、有利さは変わらないということです。
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
マイナス評価の伝え方
上司が部下にマイナス評価を付ける際の「覚悟」、それは「来期に必ず部下を成長させる」という気持ちです。マイナスの評価をつけた部下を成長させるために、上司は部下に対して何をしなくてはならないのでしょうか? ポイントは、部下に求められる標準的な行動に即して評価基準を定め、具体的に行動レベルで部下に伝えるという面談の仕方にあります。しっかりした基準があれば、評価は感覚ではなく行動レベルで下され、日常的な行動・成果を通じて伝えられると期待されます。「部下を成長させたい」という気持ちに立脚した評価基準こそ、評価者の姿勢です。
-
部下育成
-
-

-
管理職
管理職の「3つのタブー」とは?
組織のヒト・カネ・モノをうまく活用し、またリーダーとして、ビジョンを描き、部下のベクトルを合わせるのも管理職の役割です。そんな管理職がマネジメントでやってはいけない3つのタブーがあります。できる管理職になるには、この3つのタブーを踏んではいけません。しっかり部下を育て、自ら動くのではなくメンバーを動かし、品質を絶えずチェックし、大きな方向性をとらえ、メンバーを正しく導いて仕事の成果を出す。これができる管理職に必要なスキルです。
-
業務管理
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
KPIを使って強い組織をつくる!
KPIの活用は実践的な管理手法の一つです。管理職は、自部署の成果をあげ続けるという点にこだわります。したがって、一過性ではなく継続的に目標を達成していく組織を築くために、KPIという経営管理の手法をいかに自分のものとして活用するかが大切です。KPIと聞くと、組織のトップだけのもので、自分には関係ないと思われる方もいらっしゃいますが、業務や部下をマネジメントなど職場において非常に有効です。日常業務の基本フローであるPDCAをまわす際に、常に指針となるものです。自部署の方針・目標と連携させ、達成度の見える化がタイムリーにわかるため、日常の業務管理や育成に活用できます。強い組織をつくる上で大変有効な手段です。
-
業務管理
-
部下育成
-
-

-
管理職
非正規社員を活用する!
シニア世代の活用は働き方改革の大きなテーマの1つです。シニア世代の豊富なビジネス経験をノウハウとしてうまく活用することも生産性向上の一助になり得ます。管理職のマネジメントには職場環境改善、非効率な仕事の見直しも含まれます。正規社員だけでなく、非正規社員、パートタイム、アルバイトと人間関係を築きモチベーションアップに努めることも重要な任務です。非正規職員の能力を活かし、成果を認める環境づくりに管理職のマネジメント能力が試されているという点かもしれません。
-
部下育成
-
-

-
管理職
管理職が理解しておくべきPDCAの本質とは?
PDCAとは仕事を正しく進めていくうえでの「プロセス管理」であり、管理職が、自身の部門業務をマネジメントするために必要なツールです。今回はPDCAが上手くいかない理由と、管理職が理解しておくべきPDCAの本質についてお伝えします。
-
業務管理
-
部下育成
-
-

-
管理職
管理職は何をマネジメントするのか?
管理職に求められる最大の役割は、マネジメントです。とはいえ、マネジメントという言葉が何を指すのかが曖昧になってしまっていることがよくあります。今回は管理職がすべき、3つの具体的なマネジメントについてお伝えします。
-
業務管理
-
-

-
管理職
ダイバーシティ・マネジメント
ダイバーシティ・マネジメントとは社員1人ひとりが持つ多様な特性を受け入れ、活かすことで、企業・組織の力を高めることです。典型例は子育て中の女性です。このダイバーシティ・マネジメントにはタイムマネジメントが不可欠です。皆さまの職場はいかがでしょうか?
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
上司にホウ・レン・ソウする ~管理職のためのホウ・レン・ソウ(2)
今回は、管理職が上司に対してどのようなホウ・レン・ソウをするべきか、組織の中での立ち振る舞いをお話します。巧みな根回しや、要点を掴んだホウ・レン・ソウなど忙しい上司にホウ・レン・ソウし、段取りが良くデキル人と思われるには、それなりのコツがあるんです。
-
業務管理
-
-

-
管理職
部下にホウ・レン・ソウさせる ~管理職のためのホウ・レン・ソウ(1)
「悪い情報ほどまっさきにホウ・レン・ソウしてほしい」など、今回は上司として、部下にどんなホウ・レン・ソウをしてほしいのかという観点で考えてみます。最も大切なのは会社において自分を「見える化」するということです。
-
部下育成
-
-

-
管理職
今日からできる! 管理職のためのビジネス文書指導法
文書力は指導することで想像以上に簡単に伸ばすことができます。「書く」ことの上達は、結果的に報告能力や仕事の手順の効率化など、業務遂行能力の向上にもつながります。職場全体でよく使うビジネス文書を分類し、文書の作成方法を標準化していく事が有効です。
-
部下育成
-
-

-
管理職
部下のモチベーション低下を食い止める
人は誰しも、楽しく前向きに働きたいと思っています。部下を動機づけ、パフォーマンスを最大化することは、管理職の主たる仕事の一つです。部下のモチベーション低下を未然に防ぐには、部下がモチベーション高く働ける環境を作ることが重要です。
-
部下育成
-
-

-
管理職
「検査のための検査」をしてしまう危険性 ~コンプライアンスを上手くやるポイント(3)
既存の業務分野のコンプライアンスチェックは、大げさに考える必要はなく、事務フローの見直しをして重要なチェック項目が何かということだけにしぼりこみ、シンプルにするのが一番です。
-
業務管理
-
-

-
管理職
マニュアルはコンパクトに ~コンプライアンスを上手くやるポイント(2)
現状、コンプライアンスがうまくいっている組織はあまり多くありません。チェック項目をたくさん設けて、却って滞ってしまうなど、余計な手間が新たなミスの元になるというケースもよく見られます。コンプライアンスの前提として、仕事自体のフローを見直して、その工程をできるだけ減らすということをやらなければいけません。
-
業務管理
-
-

-
管理職
リストでチェックする ~コンプライアンスを上手くやるポイント(1)
あなたの会社に誰も見ない分厚いマニュアルが眠っていませんか?思い当たる方はにはこの記事を読むことをおすすめします。コンプライアンスを上手くやる最重要ポイントは「事務処理」と「捨てる」です。
-
業務管理
-
-

-
管理職
「仕事の標準化」で業務改善とリスク管理の両立
「仕事の標準化」を徹底することで、リスクは間違いなく軽減し、さらに業務改善にもつながります。標準化のためのキーワードは、「機械化」、「分業」、「集約」です。
-
業務管理
-
-

-
管理職
事務リスクを管理するには?(2)
事務リスクを洗い出すためには、前述したとおり、まず、業務を整理することです。 そこで、今回は「業務洗い出し・リスク評価・対応シート」を使って業務の整理を実践的に実施していきます。
-
業務管理
-
-

-
管理職
事務リスクを管理するには?(1)
仕事の効率化によるコスト削減を目的に業務改善活動が行われる一方で、トラブルやクレームを防止・回避するためのリスク管理に対する仕事の比重が高まっています。リスク管理において最も身近なものに「事務リスク」があります中には、マスコミを賑わすような大事件に発展するものも少なからずあります。
-
業務管理
-
-
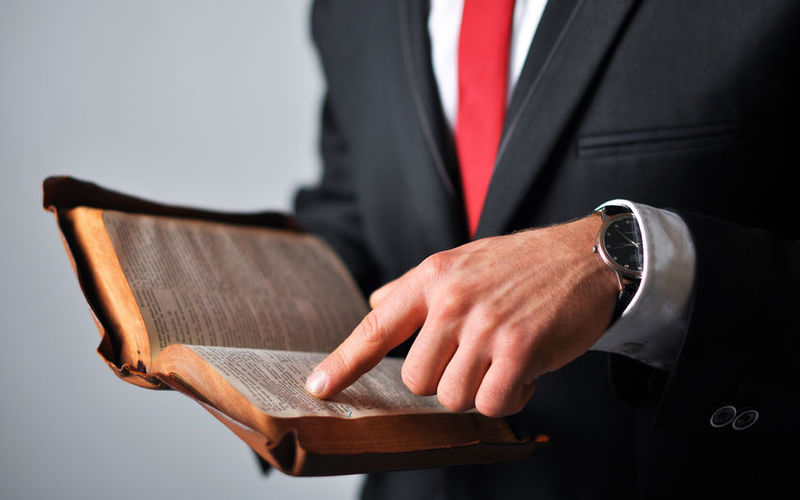
-
管理職
リスク管理は上司の仕事
上司の仕事は、部下や周囲の人を動かすことですが、「リスク管理」は、絶対に自分でやらなければいけない仕事です。部下に仕事を任せ、結果を確認するのは業務上当然です。ただし、自分でも1回は実施してみることが重要です。
-
経営者の視点
-
-

-
管理職
仕事を任せる ~中堅・リーダーを育てる
中堅や自分の補佐を育てる際には、「仕事を任せる」ことが効果的です。仕事を任せるといっても、丸投げにはせず、しっかりと権限委譲をしたうえで、任せることが重要です。 権限委譲と丸投げの違いは紙一重です。丸投げは部下のモチベーションに多大な悪影響を及ぼします。
-
部下育成
-
-

-
管理職
応用が利くように指導する ~新人・若手を育てる2
Aという業務があった場合に、なぜBという対応をとるのか? その理由を語れば、A以外の業務についても想像力を働かせて、対策を予想することができます。何度も何度も、理由を語るうちに、初めて見る業務に対しても、どう動けば良いかを考える予想をすることができ、自力で対応できるようになってきます。
-
部下育成
-
-

-
管理職
鉄は熱いうちに打て! ~新人・若手を育てる1
管理職研修で、受講者の方からよく挙がるのは「業務と平行して部下を育成するのは難しい」というご意見です。鉄は熱いうちに打てと言いますが、入りたて・異動したての時期は、教えるタイミングとして最適です。
-
部下育成
-





