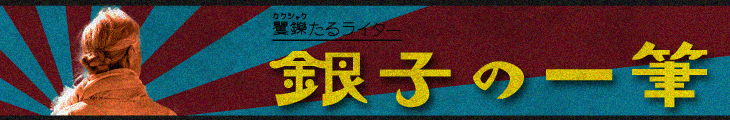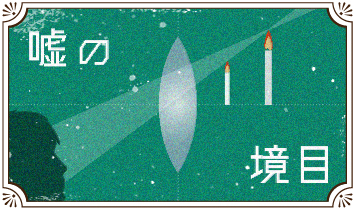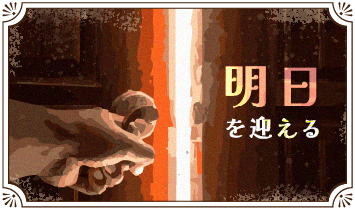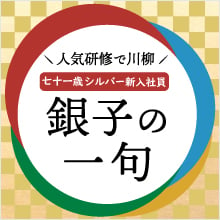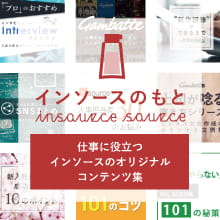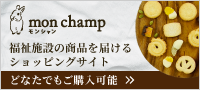開け放した窓から、緑の香りを含んだ風が入ってくる。少なくなったという雀の姿を目で探しながら、新茶を味わう。年々貴重になってくる穏やかな季節を楽しもう。やがて来る過酷な夏に向けて、今のうちに柔らかな気持ち・めげない体力を蓄えて免疫力を高めておこう。
昔、ある新婚夫婦が各々の馬に乗って楽しく散策中、何かに驚いたのか馬が急に激しい動きをして妻を落馬させた。妻を介抱した後、夫は馬に向かって「1!」と言った。後日、散策中にまた同じことがあった。夫は馬に向かって「2!」と言った。そのまた後日、3度目に妻を落馬させた時は、「3!」と言って馬を射殺した。見ていた妻は驚き「なんという酷いことを!」と夫を激しく責めた。黙って聞いていた夫は、話終わった妻に向かって「1!」と言った。
かつて読んだ(定かではないが多分)イギリスの小噺だ。
■仏の顔も三度
私たちの日常にも同様の反応が起きることがある。例えば、家電の不調を感じ始めて業者を呼ぶ、または買い替えるまでの不具合の頻度。おいしかった団子の味が変わった店で買わなくなるまでに。鉢植えがいつも根腐れを起こす場合。待ち合わせの度に大幅な遅刻をする人に。一度や二度なら、たまたま・偶然という事もあろうが3度になると見過ごせないと思い始める。事情は違っても、人はどこかで我慢や許容の限度を決めているのかも知れない。
時には部下の度重なる失敗に対して堪忍袋の緒を切らせて、逆にハラスメントに問われる人もいる。が、これはまた少し違うと思う。経験の少ない部下が同じ失敗を何回も繰り返すのは、指導法か指示の仕方または仕事の手順そのものに不備があるのかも知れない、と気づく機会になることもある。
■効果逆効果
日本では数字、特に三・五・七に因む言葉が多く、俳句・川柳・短歌など詩歌、標語やことわざ・歌謡にも多く取り入れられている。石の上にも三年・三度目の正直・三人寄れば文殊の知恵など、故事や縁起の良し悪し・真偽のほどは別にしても、耳に語呂よく心理的に区切りがいいのだろう。
文言に数字が入ると信憑性が増し注視させる心理的な効果があるのは、日頃のプレゼンテーションや文書の見出しなどでも確認されている。また、第三者というとそれだけで利害関係のない公正な判断をする役割が明確に伝わる気がする。数字がもつ本来の意味とは別に、使い方で見えない雰囲気を強調して伝える効果がある。日本語は面白い。
けれど要注意。使い方によっては違った伝わり方になって、本意とは異なる新しいニュアンスが生まれて傷付く人がいるかも知れない。〇〇100倍計画・△△ゼロ計画など、具体的な目標ではなく根拠のない極端な数字で鼓舞しようとすると、表面的で実がない調子のよさから却って届かない・響かないこともある。
一方、日夜少しの数字の変化が命を左右する目途になる人もいる。たった~・わずか~・~もの、がどれほど人の気持ちを逆なですることか。と思えば、場所によっては軽々には使えない。日本語は難しい。
1973年第一次オイルショックの頃、当時天才の名を欲しいままにしたコピーライターが、「リッチでないのに、リッチな世界など分かりません。~~~嘘をついてもバレるものです」といって業界に大きな衝撃を与えた。同業者だというだけで彼の個人的なことは知らなくても、多分みんな自分の仕事について改めて考えたはずだ。日本語・数字、表現・ニュアンスなど見えない真偽の交錯を調整する、面白いが難しい仕事だと実感したはずだ。以降、私は「いつも本当のことを言っている訳ではないけれど、決して嘘はつかない」と自戒し、基準にして仕事をしてきた。同様に世の中を少し疑い、少し信じている。
2025年5月7日 (水) 銀子