
![]()
- 01 報告書の構成
- 02 報告書を上手に書くテクニック
- 03 報告書の具体的な書き方
- 04 報告書の詳細な内容のポイント
- 05 社内報告書文例集

![]()
ビジネスに役立つ文例集
報告書とは、上司や関係者に必要な情報を提供するための文書のことです。3層構造(標題→内容要旨→詳細内容)で、情報の整理や要約をしていきます。
例えば、日時、場所、目的、内容等について、情報を簡潔に記入します。
また、所感は記入する場合と、しない場合があります。その場の細かなニュアンスを伝えたほうが有効な場合には、所感も書くようにします。
【報告書(例)】
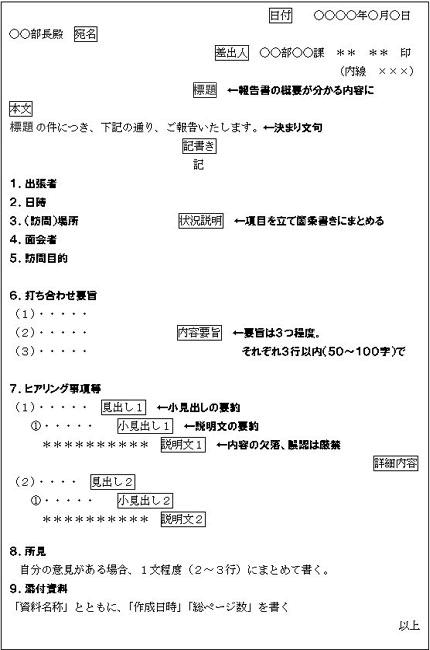
注意すべき点は、以下の三角形の図のように、「標題」は「内容要旨」(打ち合わせ内容)の要約、 「内容要旨」は「詳細内容」(ヒアリング事項等)の要約という3層構造を理解することです。 実際、報告書を上から(標題から)順に書こうとするから難しいのであって、 報告書の説明文(詳細内容から)順に書いていけば、割と楽に書けます。
【報告書の構造(下位にいくほど詳細な説明)】
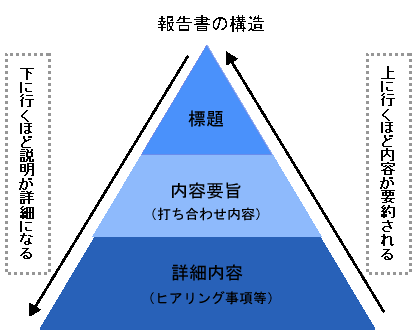
説明文(「詳細内容」)にも、同じような三角形のピラミッド構造があります。 「見出し」は「小見出し」の要約、「小見出し」は「説明文」の要約というように、 ここでも、下位の文章を先に書いて、徐々に上位の見出しをつけていく作業を 順々に実施していけば、詳細内容を楽に書くことができます。
【詳細内容の構成】
【報告書の構造(下位にいくほど詳細な説明)】
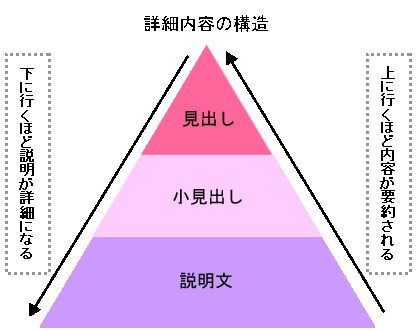
報告書の形式・分量、内容は「誰に」「何の目的で」報告書を提出するのかによって異なります。それぞれ目的にあった「まとめ方」が必要です。
(1)トップ・役員へ提出する報告書
【内容】大口の商談、大きなトラブル、重大な環境変化、重大な情報(ライバル社の重大な動向)等
【形式・分量】A4用紙1枚程度で要旨のみ(約200字程度)
【特徴】所見は必ずつける。また、すみやかに提出する
【ポイント】
立場が上の方は忙しいので、少ない文字数で専門用語などを極力控えて、分かり易く書きます。また、経営判断にかかわる内容であるので、報告書はいち早く提出する必要があります。所見をかならずつけ、判断の助言をします(偉い人は現場の詳細な事まで知らない事が多いので、現場担当者の意見をまず聞く事が多い)。自分の仕事が認められ、抜擢されるチャンスでもあるので、気合いを入れて書いてください。
(2)上司、先輩など部署内で出す報告書
【内容】商談、業務内容、出張、研修、トラブル、ライバル社の動向 等、通常業務における報告
【形式・分量】要旨をA4用紙1枚程度、詳細内容を書く必要があれば、2~3枚作成
【特徴】所見は必要に応じてつける(必要かどうか聞く)、提出は翌日が望ましい。遅くとも数日以内が基本
【ポイント】
まず、報告目的にもよるが、「簡単に書け」と言われれば、200字以内(要旨のみで可)で書く。「詳細に知りたい」と言われれば、「要旨」+「詳細内容」の構成で書きます。
組織内の報告書を素早く作成するためには、形式・内容について、まず、「前例踏襲」すべきです。さもなければ、上司に形式を相談してから作成すべきです。
何も指示がなければ、できるだけ詳細に書いた方が後で業務の役に立ちます。特に商談や業務報告は上司といえども、細かい部分が書かれていないと判断できないので、できるだけ詳細に書くべきです。
(3)お客さまに出す報告書
【内容】トラブル報告、調査報告 等、会社対会社で実施する報告
【形式・分量】要旨をA4用紙1枚程度、詳細内容を2~3枚作成
【特徴】所見は不要。提出は報告期限までに提出する
【ポイント】
文書形式は2段構えです。要約を1枚作成し、詳細内容を別紙として作るのが基本です。提出先の社内での報告書利用方法を想定すると、この形式が喜ばれます。要約は上司などの立場が上の方へ、詳細内容は現場担当者が必要とします。
形式、内容については、自組織向け報告書の何倍もチェックが必要です。内容がまずい(事実誤認、間違い)があればトラブル(最悪、訴えられる)事も考えられます。提出前に法務担当部署の確認を取るなどは常識です。自分の判断で勝手に提出しない事。
加えて、注意を要するのが「儀礼に反しないか」の確認です。相手の心象が極端に悪くなります。
【注意点】
文字量に留意しながら報告書を作成すると、目的にあった上手な報告書が書けます。
●「ですます調」と「である調」の混同をしない
一気に文書を書き上げた場合には、特に見直しが必要です。必ず読み直して、チェックしましょう。
●助詞の重複を避ける
同じ助詞が3回以上連続すると読みにくくなります。そのような場合は文章を分割する等、構成や表現を変えましょう。
●句読点の打ち方
文章の末尾には句点(。)を打ちます。読点(、)の使い方には明確な規則はありませんが、基本的には以下のようなケースで打ちます。
報告書を提出する際、口頭で内容の説明を求められる事が多々あります。ですから、報告書の内容・枚数にかかわらず、一言(15秒、50文字)、1分(200字程度)で内容を声に出して説明できるか確認すべきです。
忙しい上司や顧客は、報告書を読むに値するかどうかを、資料の「ぱっと見の美しさ」からまず判断します。見栄えにも配慮があれば、内容もよく吟味され、確かだと見なされます。
「見栄えが美しい」3つのポイント
(1)標題
文書の概要が一目で伝わるように15~20字で具体的に書きます。
日付、具体的な報告内容を標題に込めると内容を理解しやすくなります(よって、中身を詳しく読んでくれる事となります)。
(2)本文
簡潔に「標題(掲題)の件につき、下記の通り、ご報告いたします」と書きます。その後で、文書の場合は「記」と真ん中に記して、箇条書きで各項目を続ける(メールの場合は「記」を省略する)。
最後は「以上」で締める。
(3)状況説明
状況説明は項目分けして箇条書きにして書きます。将来、万一、将来、トラブルが発生した場合には重要な証拠にもなりますので、あくまで正確に書いてください。
(例)状況説明
(4)要旨の作り方~重要な内容を3つ程度でまとめる
先に述べた通り、要旨は文章を作って、その内容を要約し、最後に作るべきものです。報告書に「内容要旨」が必要な理由は、読み手がそこを見て、すぐに報告書の「結果」(結論)が理解できるためです。報告書を読むのは、自分より立場が上で、忙しく、報告書の文書などで余計な時間を取りたくないと考えている方です。
①こんな内容なら、上司はここを読むだけで内容が分かり、次の対応の判断を下すことが可能。もし、簡潔な報告書を求められたら、ここまでの内容で十分に報告書になります。
②重要なのは、結果を報告するだけではなく、次に「どのようなアクションをするか」ということを報告書に盛り込むことです。
【提出を受ける側から見た報告書のポイント】
報告書を読んだ後、上司が次の行動にいち早く、そして確実に移るために必要な事柄が求められる。
「詳細内容(ヒアリング事項等)」は、報告の「内容要旨」の部分を受けて、さらに詳細な内容を説明する所です。
本文の形式
「見出し」→「小見出し」→「説明文」の3つの階層をつけて書くとわかりやすい。
○3つの関係
「見出し」の説明が「小見出し」
「小見出し」の詳細が「説明文」
●逆に見れば
「説明文」の要約が「小見出し」
「小見出し」の要約が「見出し」
~ビジネス文書全体がこの形になっている
報告書内容の注意点
1.内容に欠落がないか
報告書においては、内容に欠落があっては、役に立ちません。まず、数字(金額、日時、時期、数量 等)、固有名詞(商品名、場所、名前 等)、単位(千、万、円、ドル、グラム、Kg 等)、相手の意志(反対する、賛成する、購入する、購入しない 等)を報告書から漏らしてはいけません。読み手に「悟ってもらう」事はありえません。ビジネス文書では相手は、自分の文章を「最も批判的に読む」と考えるべきです。
自分に都合良く、相手が解釈してくれることは絶対にありえません。報告書を書き上げたら、妥当かどうかを確認してください。
2.内容に誤認がないか
・数字(金額、日時、時期、数量 等)
・固有名詞(商品名、場所、名前 等)
・単位(千、万、円、ドル 等)
・相手の意志(反対、賛成、購入する、購入しない 等)
を勝手に解釈して、事実誤認しないようにしましょう。誤認によって、今後の動きが違ってくる可能性があるので、事実を正確に把握することはきわめて重要です。
これを防ぐには、メモを取るときに、重要だと思う点にサインをつけておき、商談・会議の終わりに再確認するのが望ましいと思います。
3.同じ内容はまとめて書く
・希望的観測は厳禁
・業務上、書くべき事は必ず書く(業務を知る)
・報告書の中に、課題は何か?が明確に書かれている
それ以外の部分の書き方
宛名:
役職の後に「殿」をつける組織とつけない組織がある。一般的には、組織としての書き方を上司・先輩に聞いた方がいい。
氏名の記入と押印:
報告書には自分の部署と名前を書いて、押印する。その際、印はまっすぐ(か、やや左向き(お辞儀をしているように?))に押すこと。
照会先電話:
自分の名前の下に、内線表示などの連絡先を書く場合もある。
項番のつけ方:
・「1」→「(1)」→「a」
・「1」→「1-1」→「1-1-1」など、
これも、組織によってルールが決まっているものなので、それにしたがって書く。
所見(所感)
「所見」は記す場合と、そうでない場合があります。「所見」は、伝えておきたい自分の意見がある場合や、先方の表情や態度などの場の細かなニュアンスなどを報告した方が良いと思ったら、それを1文程度にまとめて書くようにしましょう。
「所見」には自分の意見が入ってもかまいませんが、極力、自分の主観や推測を入れてはいけません。報告書は"事実"を報告するものです。特に希望的観測は厳禁です。
添付資料
添付資料がある場合は、最後に日時・タイトル・ページ数を書く。資料には、ページ数を明記し、「別紙1」「別紙2」などのように番号を表示しておくとわかりやすい。
本コラムをご覧の方におすすめの研修はこちら!
ビジネスに役立つ文例集

公開講座・研修のご案内
ビジネス文書を上手く書くには、書き方のポイントを学ぶのが近道です!
■関連読み物一覧
公開
議事録は3段階で上達する~入社1週間・1カ月・3年目で変わる「息遣いまで伝わる書き方」
議事録を3段階で上達させる方法を整理したコラムです。入社1週間の基礎、1カ月の書式整理、3年目の社外会議対応までを扱い、息遣いまで伝わる詳細の書き方を紹介しています。読み手が判断しやすい議事録を作るための実践ポイントをまとめています。
公開
日報は3つの視点で上達する~自分語りのエッセイ化を防ぎ、業務理解を深める書き方ガイド
日報を短時間でまとめながら、業務理解を深めるための書き方を整理したコラムです。業務・成果・課題・所感を簡潔にまとめる基本から、エッセイ化を防ぐ工夫、所感に大事な点を3つ挙げる上級者の書き方までを扱い、日々の成長につながる日報作成のポイントを紹介しています。
公開
上司が今日からできる文章指導~部下のビジネス文書を読みやすくする3つの改善策
部下のビジネス文書が読みづらい背景には、書き手の立場の曖昧さや構成の乱れがあります。上司が今日から実践できる3つの改善策として、立場の明確化、読み手の流れに沿った構成、定型フォームとチェックシートの活用を整理し、文章の質を安定させる方法をまとめています。
公開
書く力が仕事の質を変える~ジャーナリングとアウトプット習慣で思考整理と成長を促す
書く習慣は、思考整理、感情の可視化、学びの定着など多くの効果をもたらします。本記事では、ジャーナリングや付箋メモを活用してアウトプット力を高める具体的な方法を解説し、人材育成の観点から組織で書く文化を根づかせるポイントを紹介します。上司と人事が実務で支援できる施策もまとめています。
公開
電話・メール・チャットを「使い間違えない」ための3原則~本音を見抜きCX(顧客体験)を最大化する
電話・メール・チャットの強みと弱みを踏まえ、相手の本音を見抜きながら最適な手段を選ぶためのポイントを整理。CX(顧客体験)を高めるためのツールの使い分け戦略が分かります。
公開
「何が言いたいの?」と言われないビジネス文書を書くための4つのテクニック
ビジネス文書の目的は、読み手に正確に情報を伝え、望むアクションを起こしてもらうことです。本記事では、読み手が理解しやすい文書を短時間で作成するためのポイントを解説します。
公開
「メニューが見づらい」と売り上げダウン?~ユニバーサルデザインで注文数アップ!
飲食店の売上低下の要因になりやすい「メニューの見づらさ」。ユニバーサルデザインを取り入れることで、ターゲット顧客に選ばれる店づくりが可能です。本記事では、具体的な改善ステップや事例を交えながら、誰にとってもわかりやすいメニュー設計のポイントを解説します。実行可能なアクションを学び、自店舗の課題解決に役立ててください。
公開
読み手の反応が変わる、ビジネスEメールの書き方~誰でも書ける「伝わる文章」の5つのコツ
業務で何気なく書いているメールですが、「伝え方」ひとつで、相手の理解度や反応が大きく変わることがあります。本記事では、ビジネスシーンで相手に届く文章を書くための基本として、すぐに実践できる5つのテクニックをご紹介します。
公開
管理職に必要な「伝える力」とは~コミュニケーション・文書作成・ワンペーパー資料作成のコツを解説
管理職に求められる「伝える力」を、コミュニケーション、文書、資料作成の3つの側面から強化し、チームの成果を最大化する方法を紹介します。
■関連シリーズ一覧
■関連商品・サービス一覧
公開
AIを活かしたビジネス文書研修~業務シーン別の活用ポイント(1日間)
公開
AI時代の構文リテラシー向上研修~アレクサンドラ・アミラーゼ構文で考える(半日間)
公開
ビジネス文章力向上講座~相手を動かす「立ち位置」「論理」「要約」「熱意」
公開
ロジカル・ライティング研修~考えを筋道立てて言語化する力を磨く
公開
(新入社員・新社会人向け)テキストコミュニケーション講座
公開
Microsoft365Copilotの使い方研修~資料作成の時間を半減する(1日間)
公開
【数学的な仕事術シリーズ】資料を数学的に見せる(魅せる)技術
公開
(新入社員・新社会人向け)やさしいビジネス文書研修~5W1Hとデジタル活用でシンプルに書く
公開
【内定者スキルアップシリーズ】基本をおさえる!ビジネスメールの書き方
人材に関するお悩み
ダイバーシティ
人的資本経営
アセスメント
採用・離職防止
リーダー・管理職
組織風土・マインド
営業・マーケティング
組織運営
部門・組織向け
サービスラインナップ
講師派遣研修
公開講座
DX教育推進
動画教材
通信教育
セミナー運営
Web制作
人材アセスメント
人事コンサル
最新WEB
講師派遣研修
公開講座
動画百貨店
最新ニュース・記事