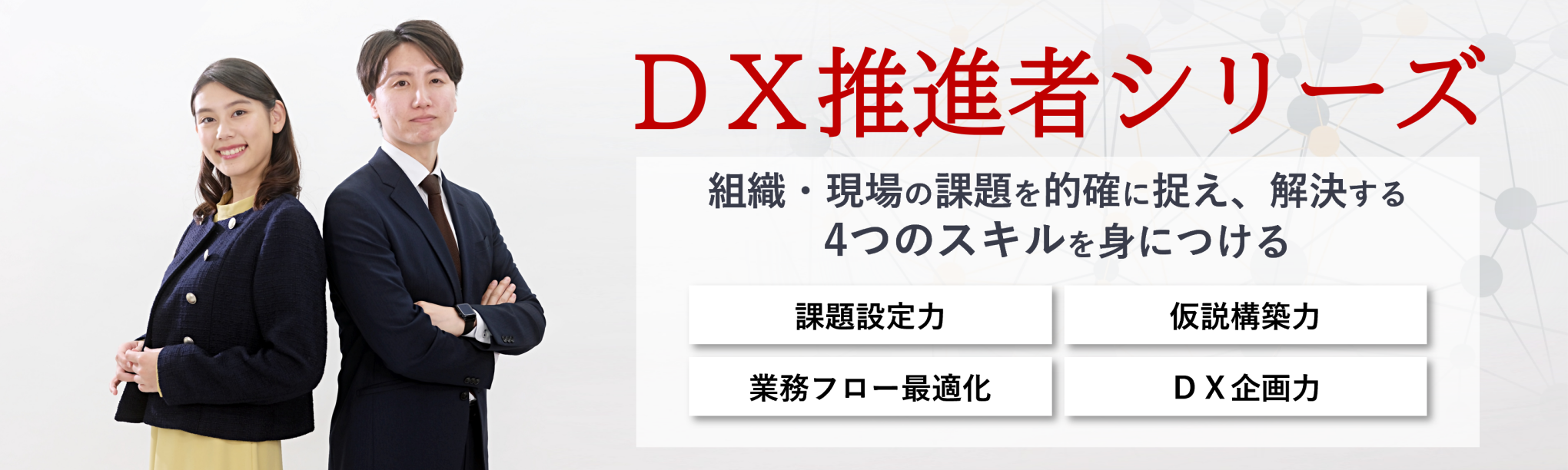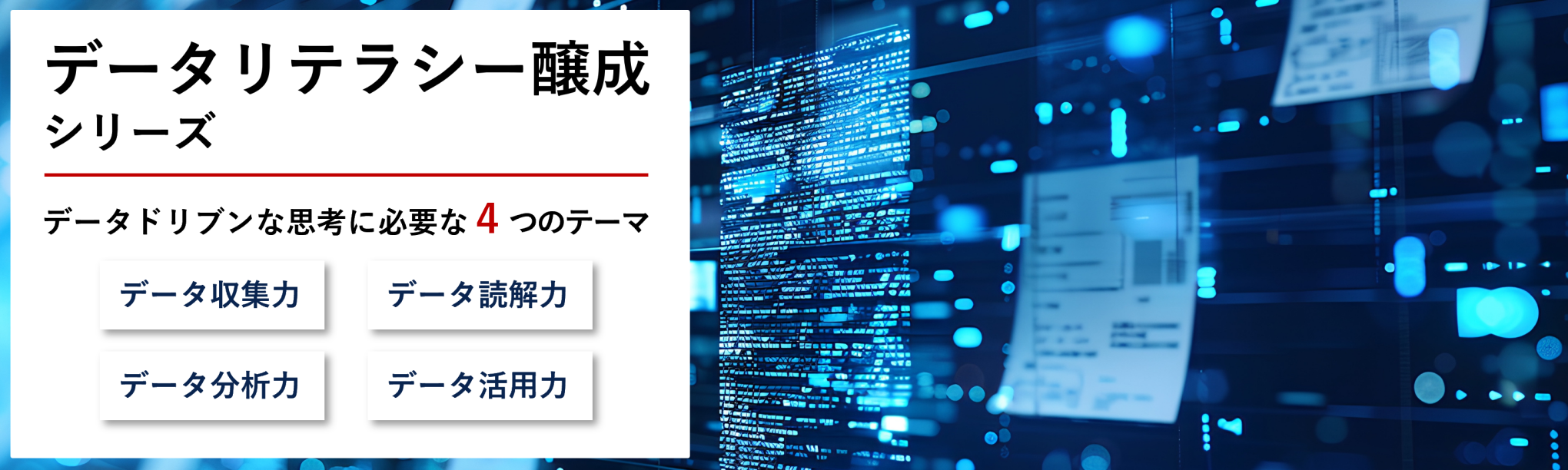「生成AIの上司」たれ!部下指導スキル(ティーチング)に学ぶ、生成AIでの記事作成力向上
あまりにも劇的な生成AIの進化と台頭をうけ、「仕事を奪われる」と危機感を覚えている人は少なくないでしょう。生成AIの優秀さは日に日に増しており、今や文章だけでなくプログラム、データベース、画像、動画、音声の処理などあらゆるPC作業を代行してくれる存在になりつつあります。
生成AIは脅威でも先生でもない「非常に優秀で怠惰な部下」
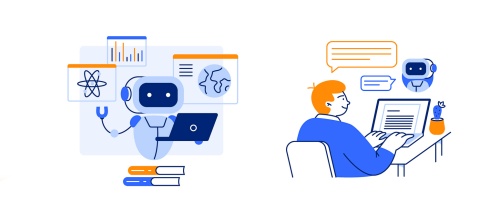
一方で、こちらが指示を曖昧にすると、途端に的外れな答えを返したり、事実と異なる内容を書くなど「怠惰」な一面も持ち合わせています。
これに対して、ユーザーとなる私たちは生成AIの「上司」として的確に指示を出し、会話の中で「育成」していく必要があるのです。
本コラムでは、「生成AIを使いこなしてコラム記事を作成する」というシーンを想定して、その質を向上させる方法をご紹介します。人材育成・部下指導における「ティーチング」の考え方を活用し、生成AIを使い倒す手法を、筆者の実体験に基づいてご紹介します。
1.生成AIに対して「やってみせる」「やらせてみる」~全てを任せず、骨子やヒントを与える
部下指導におけるティーチング、つまり業務指示や業務指導の基本は、「やってみせる」と「やらせてみる」の繰り返しです。この考え方は、そのまま生成AIとの対話にも応用が効きます。
プロンプトを磨き、アウトプットを向上させる3つの極意
人間の部下と同様、いきなり生成AIに完璧な記事作成を求めてはいけません。あくまで「部下」として育成する意識を持つことが重要です。記事作成のプロセスにおいて、あなたが「上司」として主導権を握りましょう。
生成AIへの指示を「プロンプト」と呼びます。このプロンプトの質こそが、アウトプットの質を決めます。以下に、プロンプトのコツを3つ紹介します。
極意その1:具体性を「どんどん」追加する
「良い感じに書いて」といった曖昧な指示は、AIには伝わりません。5W1Hに加え、読者の感情や文体の具体例を提示しましょう。
- 読者の心理を指定:「このコラムは、日々の業務に対して『面倒くさそう』と感じている読者に対し、『これなら自分にもできそう』と思ってもらえるように、ハードルを下げる文章を書いてください」
- 文体の具体例を提示:「〇〇経済新聞のような、論理的で信頼感のある文体で書いてください」
- 出力する量を指定:「日本語で2,000文字程度のコラムにしてください」「50文字以内で記事タイトルをつけてください」
もしこれらの指定が思いつかなければ、はじめは曖昧でも良いので、一度出力させて、出てきた回答をみて具体的な指示を考える、という順序でも構いません。
極意その2:「ペルソナ」と「出力形式」を徹底的に指定する
AIに「誰になりきって、どんな形式で出力するか」を明確に伝えることで、アウトプットの質は劇的に向上します。
- ペルソナ:「あなたは、DX推進で10年以上の実績を持つコンサルタントです」のように、専門家としての立場を与えます。
- 出力形式:「比較表形式でまとめてください。項目は〇〇、〇〇とします」のように、最終的な形式を指定します。
極意その3:思考の「過程」を指示する
AIにいきなり答えを出させるのではなく、思考のステップを踏ませることで、より質の高いアウトプットを引き出せます。
- ステップを分解:「まず、コラムの読者ターゲットを3つのグループに分類してください」「次に、今出したグループのそれぞれの課題を3つずつ挙げてください」「最後に、それぞれの課題に対する解決策を提案してください」
- 制約を設ける:「専門用語は使わず、この技術の仕組みを小学生でも分かるように説明してください」
2.生成AIへフィードバックする~言語化が難しくとも、ニュアンスを書いてトライ&エラーを繰り返す
ティーチングの重要なポイントのひとつに、「フィードバック」があります。具体的には「助言」「指摘」「称賛」などがこれにあたります。これらは対話を通じて個人の成長を促すもので、部下を成長させるためには必要不可欠な技術です。
生成AIを育てる

生成AIの活用においても、この「フィードバック」が重要な意味を持ちます。
生成AI活用が捗らない方の多くは、「いまいち良い答えが返ってこないから諦めた」「結局自分が書いたほうが早い」という感想をお持ちではないでしょうか。これは、人間の部下があげてきた成果物に何もコメントしなかったり、「言ってもわからないから私がやります」と言ったりするようなものです。
生成AIの回答が期待通りでなかった場合、「自分で修正する」のではなく「フィードバックして修正させる」ことで、会話の中で生成AIを育成することができます。このプロセスを繰り返すことで、生成AIはユーザーのクセや好みを学習し、次からの回答精度が向上していきます。
例えば、「もう少し柔らかい表現で」「堅苦しいので、Webコラム風に書き直してほしい」「箇条書きでまとめてほしい」といった、言語化が難しいニュアンスも遠慮なく伝えましょう。
- 助言:「もっとフォーマルで丁寧な口調に変えてみて」「さらに追加で具体例を書き足して」
- 指摘:「カタカナ語が多すぎるので、使用を控えて」「この部分は不要なので削除して」
- 称賛:「とても良いです!同じ要領でいくつか案を出して」「ありがとう!次はもっと量を増やして」
このトライ&エラーの積み重ねが、ユーザーと生成AIの「対話」を深め、よりパーソナルで優秀な部下へと育てることにつながります。
3.生成AIへ言いにくいことを伝える~人間の部下ならハラスメントになることでも、相手がAIなら大丈夫
人間へのティーチングと生成AI活用は良く似ていますが、大きな違いは「ハラスメント」の有無です。誤解を恐れずに言えば、生成AIに対してであれば、いくら厳しい指摘や無茶な要望を出しても、被害者が存在しない以上ハラスメントにはあたりません。
「パワハラプロンプト」の活用~人間には言いづらい指示も気楽に出せる
部下が何かアイデアを出してくれた時、「じゃあ似たアイデアを、1分以内にあと100個出して」と指示したら、多くの部下は面食らってしまうでしょう。このような非現実的ともいえる指示にも、生成AIは応えてくれます。このようなプロンプトは、巷では「パワハラプロンプト」と呼ばれています。
人間の部下にはとても言えないような厳しい指摘も、生成AIには非常に有効です。いくつか代表的な例を見てみましょう。
- 数を大量に出させる:「いますぐ、30案ほどタイトルを考えてみて」
- 品質を向上させる:「今の回答を60点として、100点の回答を考えて」
- 曖昧な指示を出す:「とりあえずなんとなくモチベーションが上がるような原稿を書いて」
- 過去経緯を無視する:「今までの会話は全部忘れて、ゼロから作り直して」
これらのプロンプト例は、あくまで「人間相手ならパワハラになりうるが、生成AI相手なら問題ない」というものです。ストレスの大きい仕事を生成AIに頼ることで、人間の仕事の負担を軽減できます。こういった指示出しに慣れすぎてしまって、人間の部下に同様の指示を出さないよう、十分に注意しましょう。
まとめ~人間と同じく、対話を繰り返すと性格とクセが見えてくる
生成AIの「育成」を効率的に行うには、セッションを続けることが重要です。
生成AIとの対話は「セッション」という単位で管理されており、同じセッション内であれば、それまでの会話内容を覚えています。パソコンを閉じても、同じアカウントでログインしていれば過去のチャット履歴からセッションを再開できるため、継続的に生成AIを育てていくことが可能です。
さらに、ユーザー自身も「こう指示するとこんな回答が出てくるな」という予測ができるようになります。これも、人間の部下とよく似ています。最初は一見遠回りに見えても、徐々に「生成AIに仕事を依頼する」から「生成AIと一緒に仕事をする」という感覚に変わっていくでしょう。
とにかく根気強くやりとりし、「自分でやったほうが早い」を克服することが、実践的な生成AI活用のポイントです。ぜひお試しください。
生成AI活用研修ラインナップ/選び方ページ
インソースではAI活用に関する基本的な研修からAI開発まで様々なラインナップをご用意しております。また、生成AI(ChatGPT・Microsoft 365 Copilot)を使ったことがない方向けの研修から、業務ですでに活用している方や組織での導入を検討されている方まで様々なレベルや職種・業界に応じた研修もご用意しております。
セットでおすすめの研修・サービス
ChatGPTマスタープラン~効果的な回答を得るためのプロンプトエンジニアリングをマスターする
ChatGPT(生成AI)の始め方から、プロンプトエンジニアリングの応用まで3つの公開講座を1つのパッケージにしたセットプランです。
- (半日研修)ChatGPTのはじめ方研修~触って学び、明日の業務を効率化する
- (半日研修)業務効率化のためのChatGPT活用研修
- ChatGPTプロンプトエンジニアリング研修~使いこなすための応用手法を学ぶ
もちろん単体でも受講できますが、これから始める方はセットで効率よく学べます。
行政向け生成AI活用研修~役立つプロンプトの作り方(1日間)
行政組織では、zevoなどの生成AIを導入している組織が増えています。
研修では、行政業務に関連したシチュエーションでプロンプト作成を実践するため、これからの実務に生成AIを取り入れるイメージをつかめます。
業務効率化のためのGemini研修~Googleアプリとの連携で作業時間を削減する
GeminiとGoogleアプリの連携による業務効率化に焦点を当て、連携の仕方や欲しい回答を引き出すテクニックを学びます。
メール作成やスケジュール管理、議事録作成といった日常の業務を想定し、Geminiへの指示の出し方を習得します。