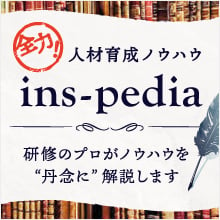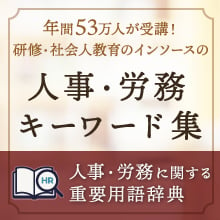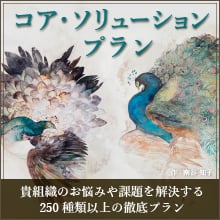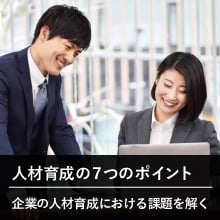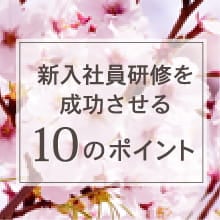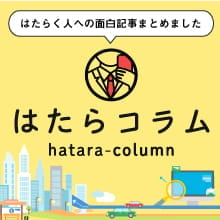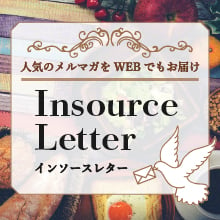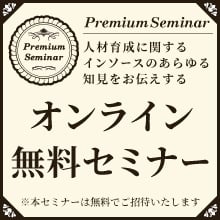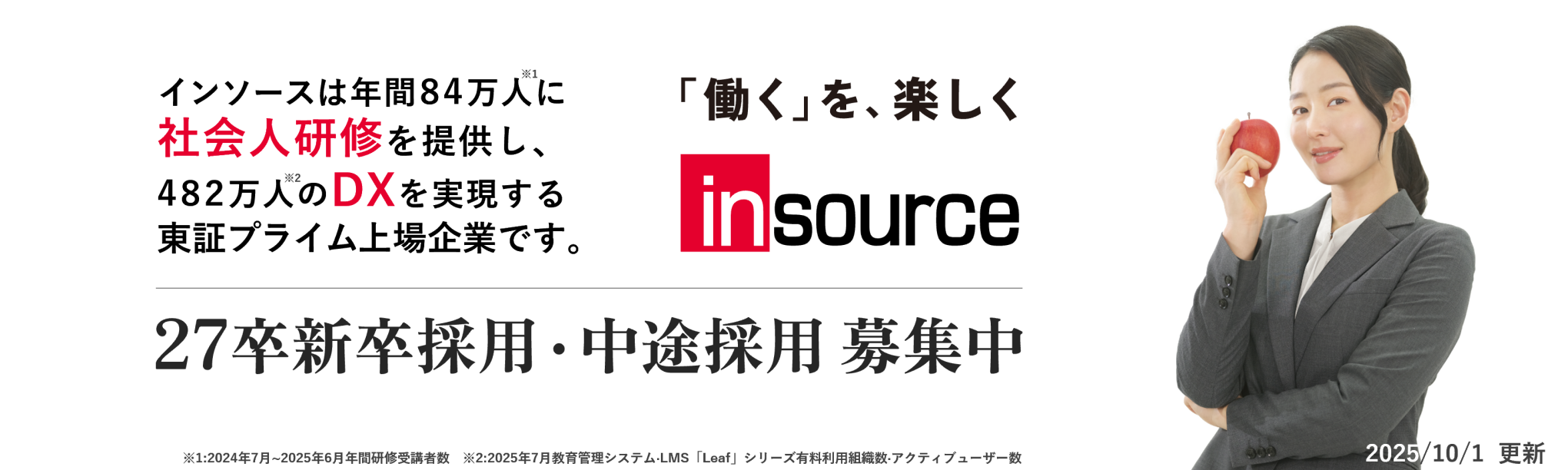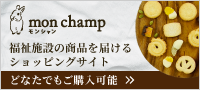2025年6月20日
日本の失業率は約3%と低めだが失業期間は約11カ月、OECD平均約8.5カ月を上回る
内閣府の令和6年度年次経済財政白書によると、上記2022年のデータから現在わが国では失業のリスクは低い一方、失業した場合には状態が長期化しやすい構造にあるとしている。
人手不足感が拡大する中、限られた労働力を就業に結び付けること、すなわち労働移動によって効率的な資源配分を実現することが重要であり、円滑な労働移動を実現するようなマッチング・メカニズムが機能する必要がある。
失業中の労働者が求人に対して応募しても、職種、業種、経験や技能等の違いから、企業側のニーズと労働者側のニーズが合わないこと(ミスマッチ要因)、また転職や職探しのプロセスには一定の時間を要すること(摩擦的要因)等から、欠員と失業とが同時に生じている。
労働市場におけるマッチングの効率性
例えば、マッチング効率性の水準をアメリカ・ドイツ・日本で比較すると、アメリカが最も高く、次いでドイツ、日本の順となっている。失業者と同数の求人がある場合、アメリカでは1か月の間に失業者の8割程度が新規雇用に結びついているのに対し、日本は3割強に過ぎず、失業状態から新たな就業への労働移動の円滑度に差がある様子がうかがえる。
2015年以前からみても、各国のマッチング効率性はほとんど変化しておらず、日本は恒常的に低い水準に位置している。
労働市場における需給ミスマッチの主な発生要因は都市部における職種間ミスマッチであることが指摘されている。コロナ禍の2022年度には若干低下したものの、我が国のミスマッチ率は11%を上回る高い水準にある。これは、新規雇用の11%以上が労働市場のミスマッチによって失われていることを示唆しており、ミスマッチ解消による効率的な資源配分の重要性を物語っている。
ミスマッチの要因
ミスマッチ率を、職種間での求人と求職に差異があることで生じている「職種間要因」と、都道府県をまたいだ労働の移動や求人と求職の調整が困難なことで生じている「都道府県間要因」をみると、コロナ禍の2020年を境にそれまで職種間要因が約7%前後と大きかったのが減少し、2022年では都道府県間要因が約7%と大きくなって逆転している。
職種間ミスマッチ率の水準は、大都市圏において高い。抜きん出て高いのは東京圏であるが、政令市のある地域の多くで全国平均を上回った水準であり、職種間ミスマッチの程度には人口規模が影響している可能性が示唆される。 結果、都市部を中心に事務や販売職は供給過剰、その他職種は広く供給過少となっている。
労働移動は同一職種内がほとんどであり、職種をまたぐ移動には課題がある。労働需給のミスマッチとの関係でみると、事務や販売など労働力の供給過剰である職種から、建設・生産・輸送など供給が過少である職種への移動は、相対的に行われにくいのが実態である。
しかし、労働市場の活性化のためには、ミスマッチを改善し過剰供給となっている職種から、過少供給となっている職種へと、職種をまたいだ労働移動を円滑化することが重要である。今後はさらに、職業訓練や教育訓練などに関する各種給付制度を通じたリ・スキリングによる能力向上支援・AI等による省力化投資などが、最も重要な取組になる。
関連サービス
- ▼【まとめ】離職防止(リテンション)を考える研修
- ▼【まとめ】オンボーディング関連研修
- ▼【講師派遣】社内転職力強化研修~今の会社でキャリアシフトを実現する
- ▼【公開講座】離職防止研修~採用者の早期活躍を支援する
- ▼【公開講座】中途採用1年目研修~即戦力として活躍する
- ▼【コラム】見通しのなさが即離職につながる~今必要なキャリア支援
最新ニュース
人事のお役立ちコンテンツ
■関連読み物一覧
■関連シリーズ一覧
■関連商品・サービス一覧
![]() 下記情報を無料でGET!!
下記情報を無料でGET!!
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ
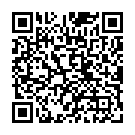
登録は左記QRコードから!
※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
人事のお役立ちニュース