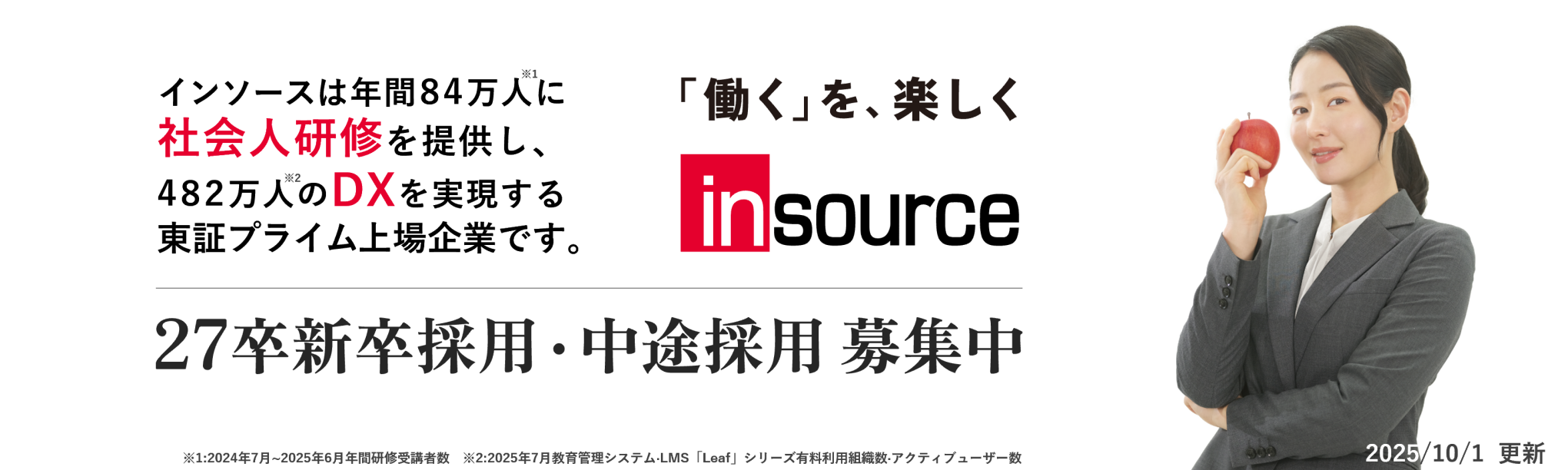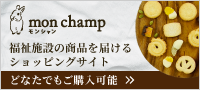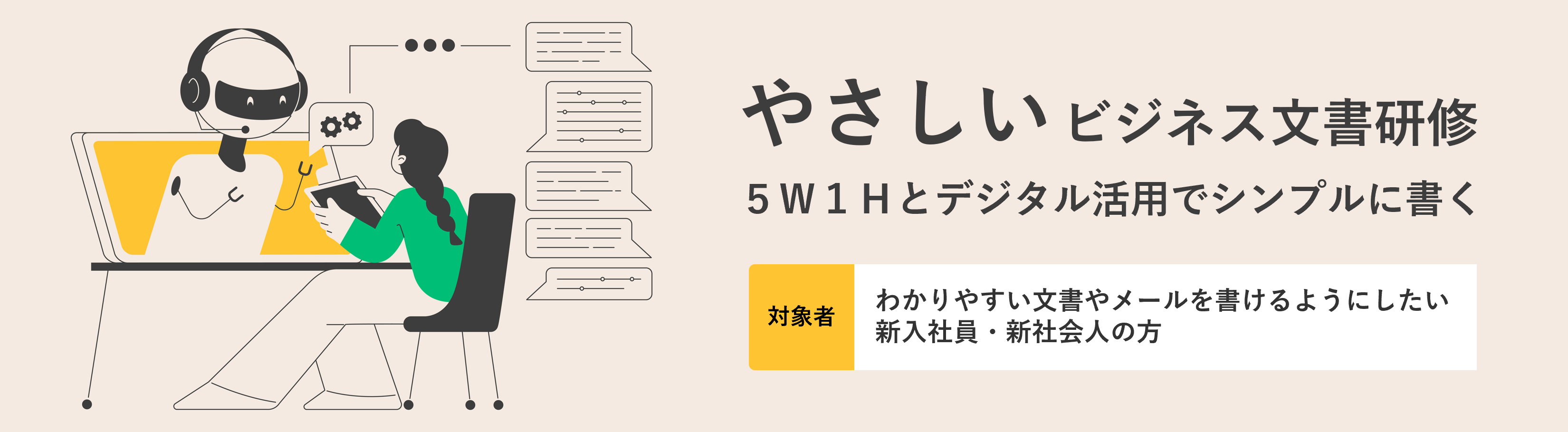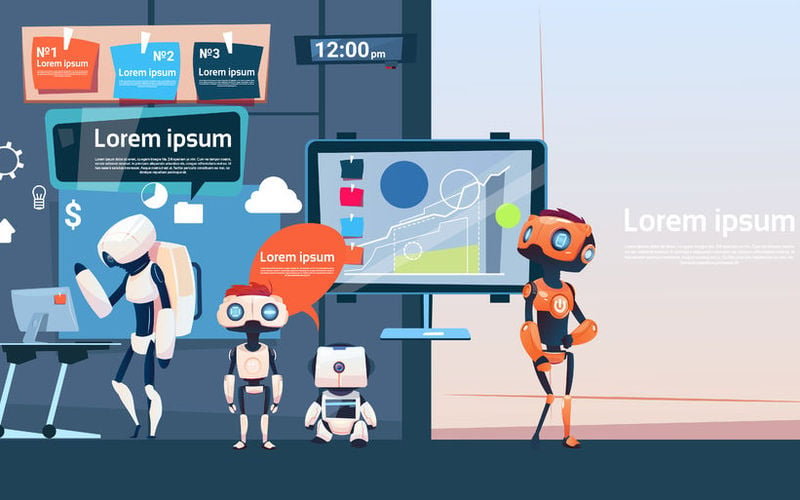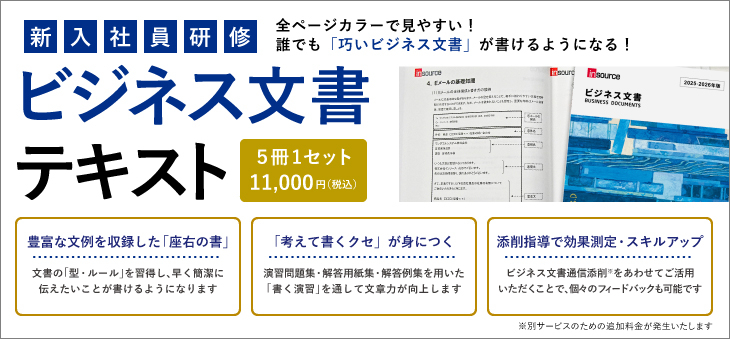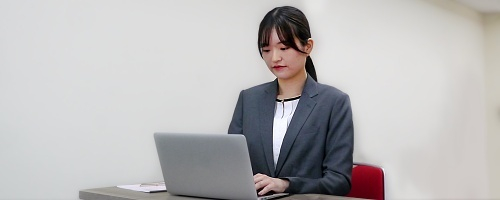読み手の心情に働きかけ、行動を促す資料とは
~「ナッジ理論」を活用した資料作成術
会議や商談で使用する資料や、宣伝に使うチラシなど、資料を作成する機会は多くあります。 しかしながら、「いつも読みづらい資料になってしまう」「相手に響かない」など、資料作成を苦手に思われている方、 もっとスキルを高めたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
資料を作成する際に必要なのは、「分かりやすく訴求力が高いコンテンツであること」です。 「訴求力が高い」とは、内容を十分にアピールできていて、読み手の欲求を呼び起こすという意味です。 「理解できた」というだけではなく、読み手が自発的に行動をとるような工夫が必要になります。
そこで本ページでは、読み手がすぐに理解できる「分かりやすい資料」とは何かをご説明するとともに、 行動経済学の「ナッジ理論」を使って読み手を動かす資料作成のコツを事例と合わせてご紹介いたします。 ぜひ最後までお読みください!
分かりやすい資料とは何か
資料を作成するにあたって、以下のようなご経験はありませんでしょうか。
・伝えたいことが絞り切れず、資料の枚数が多くなってしまう
・論点があちらこちらへずれてしまい、理解するまで時間がかかってしまう
・何が言いたい資料なのか分からない、と指摘されてしまう
資料作成において最も重要なポイントは、資料の目的・内容がはっきりしていることです。
「この資料は誰が読むのか」「読み手にどのようなアクションを起こしてほしいのか」
これらが明確になれば、必要最低限の情報を取捨選択することが可能となり、本当に伝えたいことを伝えることができます。
また、読み手が情報を素早く理解でき、迅速な判断につながります。
伝える内容が決まったあとは、全体の構成を考えます。
資料の目的・内容を考えながら、情報を整理し、その順序を決めていきます。ここでのポイントは、視線の流れに沿って、
構成することです。これにより、読み手を迷わせることなく資料の要点を伝えることができます。
最後に分かりやすく伝える工夫を施していきます。
「一文を短くすることで読み手の負担を減らす」「資料の目的に沿った適切な表現を使う」
といった要約の他、「一目見てわかるように矢印、枠、グラフを使う」といった図解が有効です。
また、専門用語やカタカナ語など特定の層にしか伝わらない言葉は使用しないことも大切です。
ナッジ理論とは何か
分かりやすい資料作成のポイントを踏まえていただいたうえで、 次に、相手が自発的に、より良い選択をするように導く「ナッジ理論」について見ていきましょう。
皆さんは「ナッジ理論」という言葉をご存じでしょうか。
ナッジ理論は、「人は感情で動く」という観点から経済活動を体系的に組み立てた学問
「行動経済学」の理論の1つです。
2017年にリチャード・セイラー教授が同理論を提唱し、ノーベル経済学賞を受賞しました。
これがきっかけとなり、企業のマーケティング戦略や公共政策に使われるなど、
現在ビジネスの場で活用が広がり、大きな注目を集めています。
ナッジ(Nudge)のもともとの意味は、「ひじで軽く突く」という意味で、
「ちょっとしたきっかけで相手により良い選択を促す」ための理論です。
特に資料や広告作成において強い効力を発揮し、読み手の行動を促した、いくつもの成功事例があります。
そんなナッジ理論ですが、「EAST(イースト)」と呼ばれるフレームワークによって構成されています。
「Easy(簡単)」「Attractive(魅力的)」「Social(社会的)」
「Timely(タイムリー)」の頭文字をとってEASTとなっており、これら4つの観点から
相手の行動を促すための工夫を考えます。
▼EASTを構成する4つの要素
E:Easy(簡単)
人は、簡単で楽な行動を選びやすい
→ 一目でわかるような資料を作成したり、選択肢を絞ることで、
行動へのハードルを下げる
A:Attractive(魅力的)
人は、自分にとって魅力的なものを選ぶ
→ 相手の注意を引きつけるような仕掛けをして、訴求力を高める
S:Social(社会的)
人は、社会規範に影響を受ける
→ 他の人がどのような行動を取っているかを伝えることで、人を動かすことができる
T:Timely(タイムリー)
人は、タイムリーなアプローチに反応しやすい
→ 適切なタイミング(相手がその情報・サービスを欲しがっている時)に
情報を提供する
ナッジ理論のフレームワーク「EAST」を使った活用事例
ナッジ理論を活用するメリットは、圧倒的なコストパフォーマンスを発揮する点です。
「資料の文言を少し変える」「情報の順番を変える」「データを差し込む」など、
"ちょっとの工夫"で成果を上げることが可能なため、多額の宣伝・PR費用を抑えることができます。
では、実際にEASTがどのようにして活用されているのか、5つの市町が実施した「がん検診の受診率をアップさせた事例」を用いてご紹介いたします。
▼E:Easy(簡単) 選択肢は少ない方が選びやすい(福井県高浜町の例)
高浜町では、がん検診の受診率を向上させるべく、新たな申込フォームを開発しました。
今までがん検診はオプションのような位置づけとして見せており、受診したいものを
住民が選んで申し込むものでした。
改善したフォームでは、「がん検診は対象となるもの全てセットで受診すること」を前提とし、
住民は検診の希望日を選ぶだけの簡単なものとなりました。
「どれにする?」から「いつにする?」に変更し、選択肢を少なくした結果、従来のフォームと比べて、17ptsアップの申込率53%と大きく向上しました。
▼A:Attractive(魅力的) 損する情報が行動を促す(東京都八王子市の例)
大腸がんを発見するためには、毎年のリピート受診が不可欠です。
八王子市では、大腸がん検診を前年度受診した人のリピート受診を促そうと、
大腸がん検査キット(採便容器)を送付しました。
しかし、送付した対象のうち、受診率は7割にとどまりました。
そこで、未受診者の受診を促そうと、以下の2種類のハガキを送付しました。
<Aグループ>
受診いただいた方には、来年度、
「大腸がん検査キット」をご自宅へお送りします。と記載。
=受診すると来年度もキットがもらえるという得がある
<Bグループ>
受診いただかない方へは、来年度、
ご自宅へ「大腸がん検査キット」をお送りすることができません。と記載。
=受診しないと、来年度はキットがもらえず、損してしまう
結果は、「損はしたくない」という損失回避に働きかけたBグループの受診率が、Aグループよりも7.2% 高い結果となりました。
▼S:Social(社会的)「他の人はどうしているか」を伝え、行動を促す (高知県高知市の例)
人は自分たちで考えているよりもずっと周りの人の行動や発言に影響を受けています。 統計データを活用することで、相手の行動を促すことができます。「2人に1人が ○○しています」「90%の人が○○しています」と資料に目立つように 記載することで、読み手の「周囲と同化したい」という意識を刺激することができます。 高知市では、周りの人は健診に行っていますよ、と数字で伝えることで、同調性を刺激して、行動を促すことに成功しました。
▼T:Timely(タイムリー) 適切なタイミングで情報を提供する (福岡県福岡市、千葉県千葉市の例)
福岡市と千葉市は、働き盛りで、家庭でも子育てや教育などに関わることから 常に忙しい40代、50 代の受診率が低かったため、携帯電話のショートメッセージを利用した施策で受診率を高めました。
・去年受診した月にショートメッセージを送信し検診の記憶を蘇らせ、予約に促す
・健診の終了1か月前にショートメッセージを送信し、駆け込み予約を促す
千葉市では、駆け込み予約を狙ったショートメッセージの送信により 25.6%が受診するという結果となりました。
参考:厚生労働省「受診率向上施策ハンドブック 明日から使えるナッジ理論」 https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000500407.pdf (最終アクセス2020年12月10日)
最後に
ナッジ理論を活用した資料作成のアイデアはいかがでしたでしょうか。
相手の行動を促す資料は、ほんの少しの工夫で作成できることがおわかりいただけたかと思います。
それに加えて「受診率を高める」という1つの目的に対して、複数のアイデアがあったように、
4つの視点からアプローチが考えられる点も、ナッジ理論の魅力の1つです。
簡単に実践できて、すぐに成果につながるナッジ理論を活用しない手はありません。
この機会にナッジ理論をもとに訴求力の高い資料を作ってみてはいかがしょうか。
<関連リンク>
【講師派遣】資料作成研修~ナッジ理論を活用し、読み手を動かす資料を作成する(1日間)
■関連読み物一覧
-
-
公開
議事録は3段階で上達する~入社1週間・1カ月・3年目で変わる「息遣いまで伝わる書き方」
議事録を3段階で上達させる方法を整理したコラムです。入社1週間の基礎、1カ月の書式整理、3年目の社外会議対応までを扱い、息遣いまで伝わる詳細の書き方を紹介しています。読み手が判断しやすい議事録を作るための実践ポイントをまとめています。
-
-
-
公開
日報は3つの視点で上達する~自分語りのエッセイ化を防ぎ、業務理解を深める書き方ガイド
日報を短時間でまとめながら、業務理解を深めるための書き方を整理したコラムです。業務・成果・課題・所感を簡潔にまとめる基本から、エッセイ化を防ぐ工夫、所感に大事な点を3つ挙げる上級者の書き方までを扱い、日々の成長につながる日報作成のポイントを紹介しています。
-
-
-
公開
上司が今日からできる文章指導~部下のビジネス文書を読みやすくする3つの改善策
部下のビジネス文書が読みづらい背景には、書き手の立場の曖昧さや構成の乱れがあります。上司が今日から実践できる3つの改善策として、立場の明確化、読み手の流れに沿った構成、定型フォームとチェックシートの活用を整理し、文章の質を安定させる方法をまとめています。
-
-
-
公開
書く力が仕事の質を変える~ジャーナリングとアウトプット習慣で思考整理と成長を促す
書く習慣は、思考整理、感情の可視化、学びの定着など多くの効果をもたらします。本記事では、ジャーナリングや付箋メモを活用してアウトプット力を高める具体的な方法を解説し、人材育成の観点から組織で書く文化を根づかせるポイントを紹介します。上司と人事が実務で支援できる施策もまとめています。
-
-
-
公開
電話・メール・チャットを「使い間違えない」ための3原則~本音を見抜きCX(顧客体験)を最大化する
電話・メール・チャットの強みと弱みを踏まえ、相手の本音を見抜きながら最適な手段を選ぶためのポイントを整理。CX(顧客体験)を高めるためのツールの使い分け戦略が分かります。
-
-
-
公開
生成AI時代のデジタルマーケティング入門~初心者が「即戦力」になるための基本5ステップと必須スキル3選
デジタルマーケティングをこれから学びたい初心者必見。生成AIを活用すれば、ペルソナ設計やカスタマージャーニーマップの作成など、複雑なマーケティング業務を効率的に進められます。本記事では、AI時代に求められるデジタルマーケティングの学び方と実践ステップをわかりやすく解説。すぐに使えるプロンプト例付きで、基礎から応用まで体系的に理解できます。
-
-
-
公開
「何が言いたいの?」と言われないビジネス文書を書くための4つのテクニック
ビジネス文書の目的は、読み手に正確に情報を伝え、望むアクションを起こしてもらうことです。本記事では、読み手が理解しやすい文書を短時間で作成するためのポイントを解説します。
-
-
-
公開
地域資源を活かした伝統産業を海外販路で開拓する実践方法
地域資源を活かした伝統産業の海外販路開拓について、海外市場のニーズ調査やブランド戦略のポイント、商品開発のステップ、海外展示会の活用法まで具体的に解説し、事業者が競争力のある商品を展開する方法を紹介します。
-
-
-
公開
「メニューが見づらい」と売り上げダウン?~ユニバーサルデザインで注文数アップ!
飲食店の売上低下の要因になりやすい「メニューの見づらさ」。ユニバーサルデザインを取り入れることで、ターゲット顧客に選ばれる店づくりが可能です。本記事では、具体的な改善ステップや事例を交えながら、誰にとってもわかりやすいメニュー設計のポイントを解説します。実行可能なアクションを学び、自店舗の課題解決に役立ててください。
-
■関連シリーズ一覧
■関連商品・サービス一覧
-
-
公開
AIを活かしたビジネス文書研修~業務シーン別の活用ポイント(1日間)
-
-
-
公開
(新入社員・新社会人向け)未来のシナリオ策定ワークショップ~業界の歴史と向き合い、社会人としての責務を自覚する
-
-
-
公開
(半日研修)SNSマーケティング研修~戦略的な運用で顧客価値を高める
-
-
-
公開
AI時代の構文リテラシー向上研修~アレクサンドラ・アミラーゼ構文で考える(半日間)
-
-
-
公開
生成AIを味方にするWebマーケティング戦略講座~AIO・LLMO対応の記事作成術で問合せを獲得する
-
-
-
公開
ビジネス文章力向上講座~相手を動かす「立ち位置」「論理」「要約」「熱意」
-
-
-
公開
実践!デザイン思考講座~事例で考えるビジネスデザイン
-
-
-
公開
ロジカル・ライティング研修~考えを筋道立てて言語化する力を磨く
-
-
-
公開
<課題解決ワークセッション>ブランド戦略策定(2日間)
-
![]() 下記情報を無料でGET!!
下記情報を無料でGET!!
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ
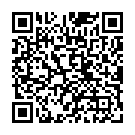
登録は左記QRコードから!
※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。