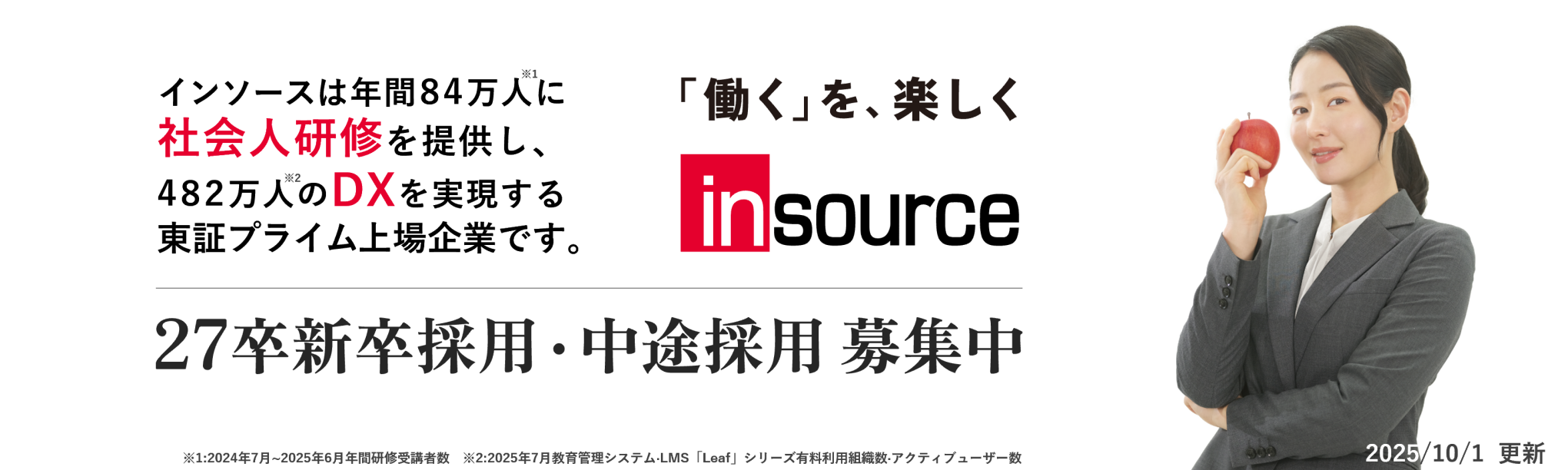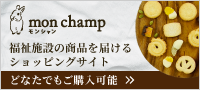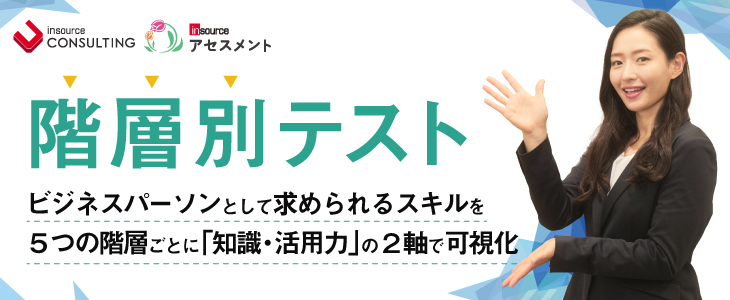人は経験から成長する
~経験学習サイクルを効果的に活かした指導法
経験学習サイクルとは、「経験から学び成長するためのフレームワーク」のことです。経験→内省→教訓→実践という4つのステップから構成されます。
本記事では、経験学習サイクルを効果的に活かしながらどのように指導を行うかということについてお伝えいたします。
▼自身の経験学習サイクルの回し方やリフレクション(振り返り)の手法について詳しく知りたい方はこちら
1.主体的な学びを加速させるエンジョイメント
経験を積み重ねて導き出した「教訓」を「持論」化するプロセスにおいて重要なのが、 経験学習に不可欠な3つの要素の1つ「エンジョイメント」です。
ストレッチで、少し背伸びした目標に挑戦することや、 リフレクションで自分の至らなさを振り返ることに比べ、 エンジョイメントは仕事の醍醐味ともいうべき喜びとなります。
経験学習サイクルを回す際に、本人が主体的に学びを加速させていく動力となります。
〇持論化のプロセスと"エンジョイメント"の関係
内省する喜び:失敗もしたけど、経験を通じて教訓を得ることができた
=失敗・成功に関わらず、成長の糧として経験をポジティブに捉える
概念化する喜び:経験で得た複数の教訓を統合すると、大事な考え方が見えてきた!
=教訓の中から本質的な要素を見出し、知的好奇心が活性化される
持論化する喜び:この考え方を当てはめていけば、次はもっと上手くいくかもしれない!
=見出した考え方をもとに次の経験に取り組むことで、よりスムーズに仕事を進めていけそうな可能性を感じる
実験・成功体験:思った通り上手くいった!持論としてどんどん活用していこう!
=実際に成功体験を味わうことで達成感を覚える。自分で考えて実行した主体的な取り組みにやりがいを感じる
このように、分析し、工夫することで手にした成果は、好奇心や達成感が刺激され、「仕事のやりがい」となっていきます。
2.エンジョイメントを得られないときの導き方
時には、経験学習サイクルを回しているのに、成長が感じられない時があります。概念化する気づきも、次の実験のひらめきも生まれない時です。何度やってもうまくいかない、思っていたような結果が出ない、「スランプ」「伸び悩み」の時期が成長にはつきものです。
しかし、成長というのは緩やかな上昇ではありません。海外に留学された経験がある方はわかると思いますが、最初のうちは現地の人の話す言葉が聞き取れない、ホームシックにかかって面白くないという日々が続きます。
が、三か月ほどたったある日、ふと耳に入った言葉が聞き取れるようになります。そこからは聞き取れるから話そうと思うし、話すから楽しくなっていく......と好循環がまわっていきます。そんな風に、ある日突然ぐんと伸びることが成長にはあるから面白いのです。
上司・先輩はスランプを「支援」することで経験学習サイクルに刺激を与えましょう。
〇伸び悩みに有効なストレッチ
上司・先輩の側から見て部下・後輩が伸び悩んでいると感じた時には、キャリアに合った「発達的挑戦(ストレッチ)」に挑戦させることを試みましょう。
<発達的挑戦(ストレッチ)の例>
ア. 本人にとって不慣れな事
本人がまだやったことのない分野の仕事や、苦手意識のある仕事を敢えて担当させる。不案内な仕事に対する理解を深めよう、うまく出来ない原因を解明しよう、といった学びが促進される
イ. 前例のない新しい事
自分自身はもちろん、上司・先輩も、また組織としても未経験の仕事にチャレンジさせる。ゼロベースで物事を発想するやり方、内部に頼れる人が誰もいない中での助力の得方、といった学びが促進される。
ウ. 高いレベルでの責任が伴う仕事
組織の代表として交渉事に関わる。仕事の成果の最終責任者となる。初めて人を管理する。このような、これまで経験したことのない重さの責任を負う立場で仕事をさせる。判断基準や優先順位の設け方、相手を説得するための論法、といった学びが促進される。
エ. 組織を横断して取り組む仕事
他部署や他社の人が混在するメンバーと関わりながら行う仕事に携わらせる。他者の視点でのものの見方、利害関係者との調整の進め方、といった学びが促進される。
発達的挑戦(ストレッチ)はキャリア上の初期・中期・後期でも異なります。適切なストレッチを設定し、没頭してチャレンジさせます。関心があるから没頭できることもあれば、没頭することで関心が深まることもあるからです。
例えば、お客さま先で常駐していたりすると、常に振り返りとアウトプットを求められるのでグッと伸びることがあります。
環境に慣れてしまったり、実践結果の予測がついてしまう経験が続くと、効率的に動こうとして新しい気づきが得にくくなります。
経験の質を高めるために新しい挑戦をする環境を整えることも上司の役割です。
3.伸び悩んでいる後輩・部下を支援するコミュニケーション
「スランプ」を経験をしている部下・後輩を導くために、上司・先輩がやってあげられることは対話です。
経験学習サイクルを自ら回せるようになった部下・後輩には「教え込む」ことより「引き出す」コーチとなることが求められます。悩みを安心して打ち明けられる場を作り、傾聴しながらもスランプの先へ導く言葉がけをしましょう。
〇成長を感じられない時も淡々と目の前のことに取り組む大切さを教える
「成長実感がない」と焦る若手社員に対して、腐らずに腰を落ち着けて取り組むことを促します。
<部下・後輩への言葉かけ例>
「腹をくくって今の仕事に集中して言うと、忘れたころに後から喜びがやってくるよ。私の場合は......(こんな経験から学んだ)」
〇伸び悩んでいる部下・後輩に対し、経験学習を促進する姿勢を教える
苦境をポジティブに転じる人は成長します。「艱難汝を玉にす(かんなんなんじをたまにす)」ということわざがありますが、苦境を経て身につく発想、思いやり、勇気、そして恐れによってその人が磨かれ、一回り大きく成長するのです。
<部下・後輩への言葉かけ例>
「責任や難易度の高い仕事や、変化が大きい環境でやる仕事は、その時は大変だけど後から絶対に良い経験になるんだ。挑戦して損はないよ。」「新しい考え方や視点を得ることもできるから柔軟に対処してみたらどうかな。」
〇部下・後輩に対し、自身の経験を語る
先を歩くメンターが持つ経験、知識の伝承と言う意味でも、経験談を聞くことには価値があります。部下・後輩が現在経験していることと照らし合わせ、上司・先輩自身の体験談を語ったり、関連するエピソードを紹介し、示唆を与えます。
<経験談を語るメリット>
・「なんだ、みんなそうだったんだ」という安心感を与える
・苦境を経て身につくことがあると肚落ちさせる
・過剰な期待を持たずに腰を落ち着けて取り組むと「仕事の面白さの兆候」を見極めることができると教える
一方、「語る」際には、押しつけがましくならないように注意が必要です。
<上司・先輩自身の体験談を語る際に注意すべき4つの点>
1. タイミングを考える
自身の体験を語るときには教育的瞬間を見抜く必要があります。ここぞというときを外した経験の語りは、説教や自慢話になってしまう可能性が高く、部下はやる気を失います。
2. 成功経験だけでなく、失敗経験を語る
失敗経験の語りは業務能力向上にとって非常に重要であるという知見が出ています。
3. プロセス(出来事の連鎖)をつまびらかにする
5W1Hを明らかにして、簡潔にまとめましょう。その経験から自分が何を感じ、何を思ったのか、そこから導き出される教訓は何なのかを話すのがよいでしょう。
例:「私が〇〇という仕事を抱えていた時に、こういう困難に出会ったんだ。自分は......と感じたが、結果的に〇〇という成功を手にすることができた。しかし、××という失敗もあって......ということを身をもって学んだよ」
4. 反論の可能性を認める
経験は、つねにどんな状況にもあてはまるとは限りません。自身の経験の中には、今のビジネス環境に照らせば時代遅れになってしまっているものもあるでしょう。そのエピソードが今に通じるものなのか、教訓に妥当性があるのかを、きちんと部下と話し合えることが重要です。
「これは私の経験だから、今の状況とは少し違うと思うけど、」と前置きして、現代においても汎用性がある教訓や信念を共に探る気持ちで語りましょう。
4.経験をプラスに活かす人に必要な5つの資質
最後になりましたが、経験学習サイクルを主体的に回せる人の"姿勢"についてお話します。
どんな経験で自分が成長するかは自身の頭の中だけでは判断できませんし、現在のような予測不可能なビジネス環境では、成長から逆算してやりたい経験だけを選ぶことも難しくなっています。
スタンフォード大学のクランボルツ教授は、様々な経験や機会をプラスに活かすプランド・ハプンスタンス・セオリー(計画された偶然理論)を提唱しました。このキャリア論の中では、以下の5つの資質が経験をプラスに活かすとされています。
<経験をプラスに活かす5つの資質>
1. 好奇心:自分の知らないことなど、どのようなことでも積極的に関心を持つ
2. 持続性:一度はじめたら、手応えや結果を出すまで、あきらめず続ける
3. 楽観性:意に沿わぬ異動や転職でも、自分のキャリアや人生の好機と捉える
4. 柔軟性:どのようなことでも受け入れられる許容力と柔軟性を持つ
5. リスクテイク:大変でも、それを乗り越えられれば、新たな成長があると考え、恐れずチャレンジする
経験に対して、以上5つの資質を意識してチャレンジしていきましょう。新たに行うことになった仕事をマイナスに捉えず、「自分の新たな可能性を試す機会」として積極的に受容していくと、経験を新たな学びとすることができます。
特に重要となるのが、経験を楽しむ好奇心とチャレンジ精神です。経験は良いことばかりではありません。難しい仕事や面倒なことを引き受けたり、失敗して恥をかいたり、苦労が伴ったりすることも多いでしょう。
しかし、「これは自分の新たな可能性を試す機会なのだ」と経験を積極的に活用する姿勢こそが、学びを深めていくのです。先の見えない時代に成長していくということは、偶然に身を任せ、その時できることを一生懸命に頑張って積み重ねること、と言えるでしょう。
まとめ
現在は、様々な意味で"余裕"がない時代ですが、短期的な成果だけでなく、中・長期的な今後を見据え、経験学習サイクルを回しながら、粘り強く、人材を育成していくことが大切です。
ただ注意すべきは、現在は環境の変化も激しいので、一度"教訓化""持論化"に成功しても、それがあまり長く通用しない恐れがあることです。教訓・持論は定期的にアップデートする必要があります。
苦労してたどり着いた教訓・持論は、本人にとって愛着があり大切にしたいものです。しかし、時代の変化により実効性が怪しくなっているのにかかわらず、それに固執しすぎると、自分の成長を止めることになります。また、部下や後輩にそれを強いてしまうと、職場全体に悪影響を及ぼすことにもなります。
若手の方も、リーダー・管理職の方も、「習うは一生」という言葉を胸に、経験学習サイクルを進化し続けていただければと思います。
<関連リンク>
【コラム】仕事における経験学習サイクルとは~4つのステップを回し、経験をノウハウに変えて成長する
【コラム】タイムマネジメントの方法・原則~なぜあの人の仕事は早いのか?
【コラム】リーダーシップのスキル強化ガイド~マネジメントやコミュニケーションとの関係
【コラム】「リフレクション」のススメ!~成長実感でモチベーションを上げる手法とは?
【公開講座】若手社員研修~経験学習サイクルを回し、自己成長を加速させる
■関連読み物一覧
-
-
公開
お金を借りるということの本質とは?~消費者金融やクレジットカードのしくみを理解して豊かな生活を実現する
お金とは単なる決済の道具ではなく、社会を循環する「血液」のような存在です。お金を借りるという意味の核心に触れ、消費者金融やクレジットカードの構造、そして個人の信用を支える信用情報機関の役割を解き明かします。
-
-
-
公開
若手社員の事務力を高める「仕事の進め方・時間管理・ミス防止」3つの鉄則
実務に慣れてきた若手社員が「指示待ち」を卒業し、自律的に成果を出すための行動指針を解説。PDCAによる仕事の進め方、効率を最大化するタイムマネジメント、信頼の土台となる事務ミス防止のメソッドを組み合わせ、業務の質を飛躍的に向上させましょう。
-
-
-
公開
新人の早期活躍は新人研修で差がつく!現場で活躍する新人育成3つの視点と、失敗しないパートナー選び4つの基準
新人研修において、新人のモチベーション維持が難しい、長期間の研修実施が負担といったお悩みはありませんか?現場で活躍する新人を育てる「3つの視点」と、失敗しない研修パートナー選びの「4つの基準」を解説します。
-
-
-
公開
ザルファ世代とは?人事・上司が知っておくべき受け入れと育成のポイント
ザルファ世代(Zalpha世代)は、デジタルネイティブながら、意外に人間関係を重視する一面も。Z世代との違いや価値観の特徴、企業・上司が受け入れる際の心構えや育成のコツを、最新の世代論とともにわかりやすく解説します。
-
-
-
公開
3年目社員は「役割が変わる」から伸びる!~仕事の点と線をつなぐことで成長が加速する
3年目社員がリーダーを目指す人材へ成長するカギは、役割転換の壁を越え「点から線」で仕事を捉える力です。本記事では支援策を解説し、実務力を体系的に高める研修も紹介します。
-
-
-
公開
「新人研修、本当に効果はある?」入社1年目が語る受けてよかった3つの研修とは
新人研修を導入しても、成長につながるか不安な人事担当者は少なくありません。今回は、新入社員が実際に経験し、仕事のやり方や考え方を変えるきっかけとなった3つの研修を紹介します。
-
-
-
公開
新入社員が自分でできるレジリエンスを高める5つの方法~OJTでは身につかない離職防止の鍵
入社して間もない新入社員の中には、真面目で責任感が強い一方で、失敗に弱く立ち直りに時間がかかる人が多くいます。OJTの指導内容を素直に実行できても、ミスをすると自信を失い、「自分は向いていない」と思い込んでしまうのです。その結果、早期離職につながることもあります。本記事では、こうした新人がレジリエンス(困難を乗り越える力)を身につけることの重要性とその方法を紹介します。
-
-
-
公開
生成AIネイティブほど成果が出ない?新入社員が成果を出すための生成AIの使い方とは
現場で成果を上げる新入社員を育てる鍵は、生成AIとの向き合い方です。学生とは異なる使い方として、武器・パートナー・実践の3つの観点から育成ポイントを整理します。
-
-
-
公開
配属前におさえるべき「当たり前」~OJT現場の負担を軽減し、新入社員の「気づく力」を育てる3つのポイント
コロナ禍で対人経験が乏しい新人が増える中、配属前に身につけたい「当たり前」の行動を解説します。仕事の流れの理解、共有物への配慮、数字で考える習慣を学ぶことで、OJT負担を減らし早期活躍につながります。
-
■関連シリーズ一覧
■関連商品・サービス一覧
-
-
公開
新人・若手向けビジネスマインド研修~理念理解と経験学習で成長基盤を築く(半日間)
-
-
-
公開
視座を上げて主体性を発揮する研修~仕事をつくり出すビジネスパーソンになる
-
-
-
公開
(新入社員・新社会人向け)ホウ・レン・ソウ実践ワークショップ(1日間)
-
-
-
公開
視座を上げて主体性を発揮する研修~仕事をつくり出すビジネスパーソンになる(1日間)
-
-
-
公開
<熱意と覚悟のマインドセット>熱い想いを叶えるプロジェクトの進め方研修
-
-
-
公開
<熱意と覚悟のマインドセット>お客さまの心を動かす熱血営業研修
-
-
-
公開
<熱意と覚悟のマインドセット>主力となる人のための仕事の進め方研修(2日間)
-
-
-
公開
(半日研修)(新入社員・新社会人向け)生成AI活用研修~社会人に必要なAIリテラシーを身につける
-
-
-
公開
インサイドセールス強化研修~戦略的に組織全体で成果をあげる
-
![]() 下記情報を無料でGET!!
下記情報を無料でGET!!
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ
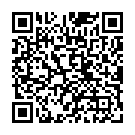
登録は左記QRコードから!
※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。