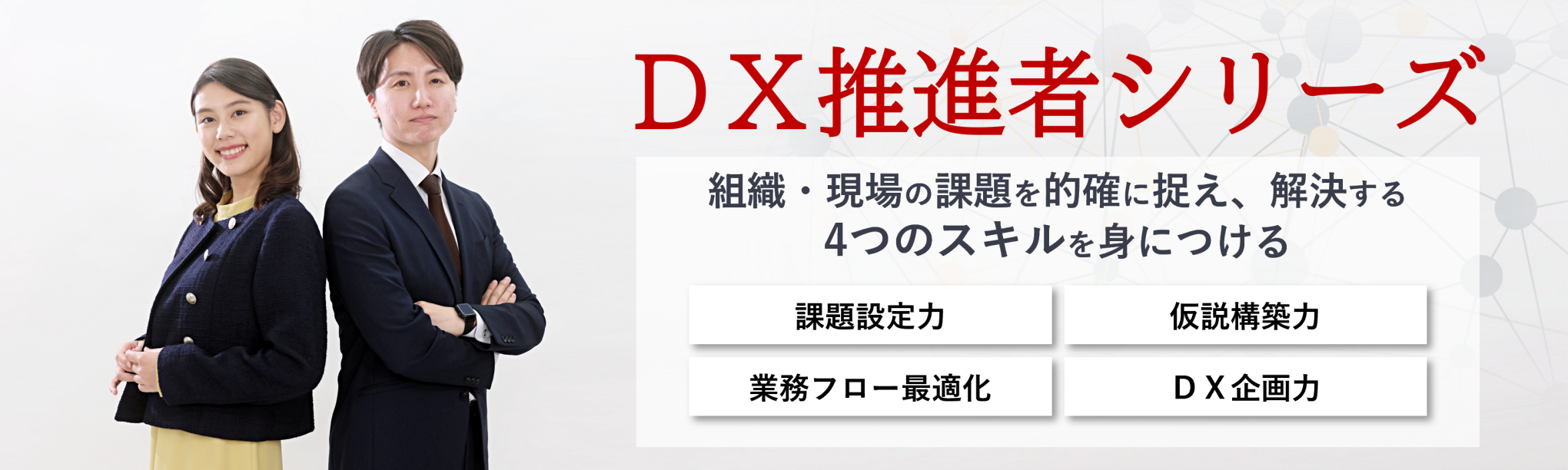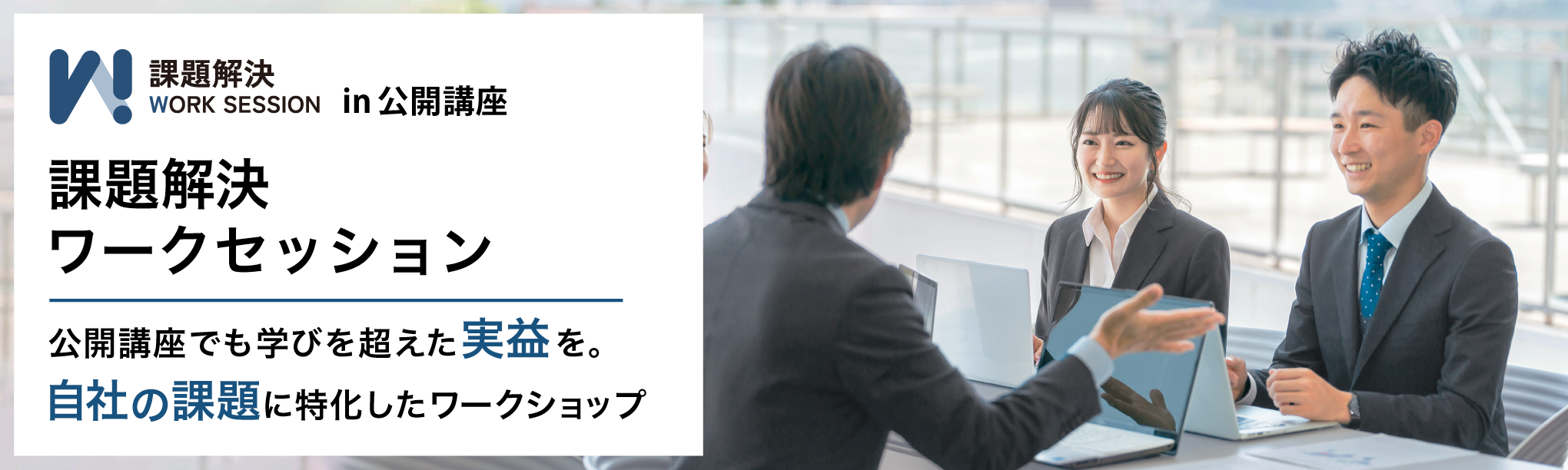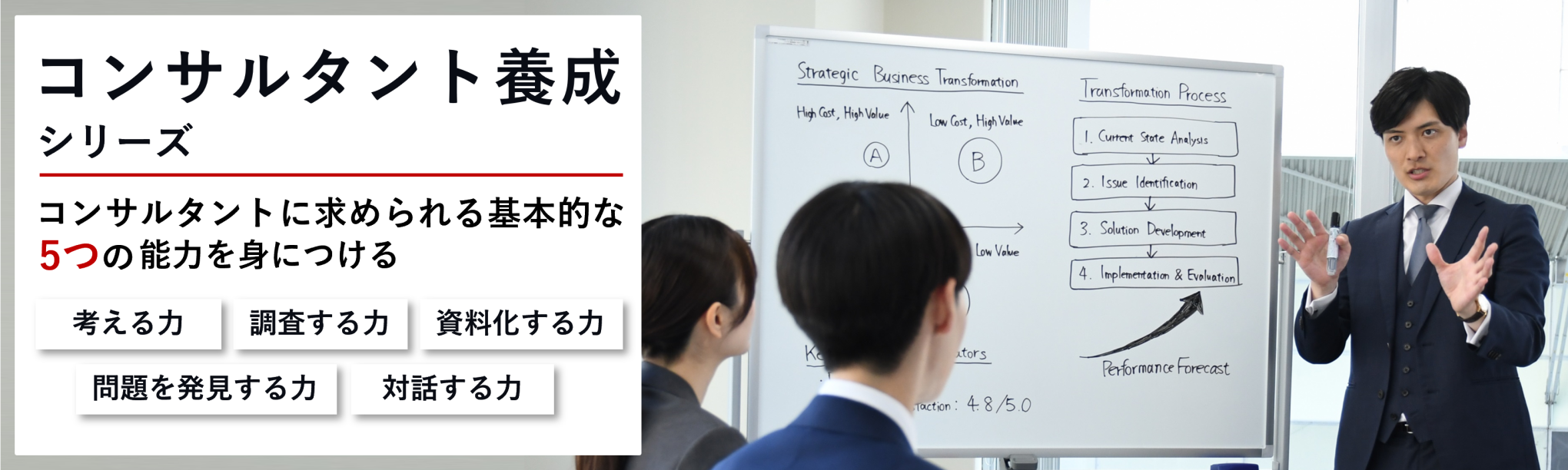成果を出すDX推進リーダーに求められる4つの力 ~非エンジニアの視点こそがカギ
経済産業省が「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」を発表してから数年が経過しました。2025年を迎えた今、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、すでに私たちの日々の業務や働き方に深く関わるテーマとなっています。

DXの本質は「テクノロジーを活用して、業務やビジネスの価値を変革していくこと」です。つまり、実務に精通している各部門の現場社員が、日々の課題を捉え、デジタルの力を活かして改善していく視点こそが、DXの鍵となるのです。
そのためには、必ずしも高度なITスキルが求められるわけではありません。今回は、非エンジニアがDXを推進するために身につけておきたい4つの力をご紹介します。
非エンジニアがDXを推進するために身につけておきたい4つの力
- 課題設定力 ~全体最適で物事を見る
- 仮説構築力 ~ツール導入前に未来を描く
- 業務フロー最適化力 ~定着する仕組みを作る
- DX企画力 ~UIの視点を持って全体像を描く
1.課題設定力 ~全体最適で物事を見る
DXを通じて期待される成果は多岐にわたります。業務の効率化、コスト削減、新たな価値創出など、その目的は企業によって異なります。ただし共通して求められるのは、「本質的な課題に気づけているかどうか」です。
例えば、日報の入力作業が煩雑で時間がかかるという現象があったとして、それだけを解消しようとすると「入力画面を使いやすくする」などの表層的な改善で終わってしまうかもしれません。しかし、そもそも日報が何のために存在し、どのように活用されているかを見直すことで、記入する内容を変更したり、他の業務プロセスに組み込むことができるかもしれません。
このように、「自分の仕事をラクにする」視点だけでなく「組織全体として何が最適か」という広い視野で課題を設定する力が、DXを成功に導く第一歩です。
2.仮説構築力 ~ツール導入前に未来を描く
課題が明確になった後は、その解決策としてどんな手段が考えられるかを洗い出す必要があります。このとき重要なのが、「仮説を立てる力」です。
例えば、高価なシステムを導入せずとも、Excelの既存機能やRPA、生成AIをうまく使うことで、十分な成果を上げられる場合もあります。手段に飛びつく前に、どんな結果を目指して、どうすればその成果を得られるのかを思い描く。この力があることで、DXはより現実的で実行可能なものになります。
新しいシステムやツールの導入には、予算や時間、場合によっては組織文化の変更も伴います。仮説構築力とは、「いくつかの選択肢を想定し、その中からコストと効果のバランスが最適なものを選び取る力」ともいえます。
3.業務フロー最適化力 ~定着する仕組みを作る
ツールやフォーマットを導入したり新たなルールを設けても、結局社内で使われなければ意味がありません。よくあるのが「せっかくシステムを整えたのに、誰も使ってくれない」というケースです。
この背景には、業務フローとの不整合や、使う側の心理的な抵抗があることが少なくありません。そこで注目したいのが、行動経済学の知見です。人間は「将来のメリット」よりも「目の前の手間」を避ける傾向があります。つまり、使いやすさや自然な導線の設計がカギになります。
使いやすい自然な導線の設計
- 必要なデータを1クリックで出せるようにする
- 業務プロセスの途中で自然に新しいシステムやルールに触れる場面を設ける
- 周囲との共有がしやすい仕組みにする
このような工夫は、言い換えればDXを「机上の空論」から現実的な改善へと引き上げる力です。新しい仕組みは、単なる導入ではなく、日常業務の一部として機能するよう最適化される必要があります。
4.DX企画力 ~UIの視点を持って全体像を描く
DX企画力として最後に挙げたいのは、「ユーザー目線でシステムやツールをデザインする力」です。ここで言う「デザイン」とは、色や見た目の話だけではありません。どの画面で、どんな操作をすれば、目的の情報や機能にたどり着けるのか。その設計全体を指します。
システム開発をエンジニアに任せきりにしてしまうと、業務の実態に合わない画面構成になってしまい、結果として「使いづらい」「現場にフィットしない」といった課題が発生します。
これを防ぐには、業務を熟知した現場担当者が、ユーザーインターフェース(UI)の基本的な考え方を理解し、エンジニアと同じ言語で会話できることが重要です。理想的な操作画面を具体的にイメージし、その意図をしっかり伝えることが、DXを「現場で使えるもの」として成功させるための最後のピースとなります。
インソースの支援:現場主導のDXを実現するために
当社では、非エンジニアの方がDXを推進していくための、実践的な研修やワークショップをご提供しています。課題設定から仮説構築、業務設計、UIの基礎知識まで、組織のDXに必要なスキルを体系的に学べるプログラムを多数ご用意しています。
現場の力を活かしたDX推進に取り組みたいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。インソースは、現場の課題に寄り添いながら、成果につながるDXの第一歩をお手伝いします。
DX推進者シリーズ~課題を的確に捉え、解決する4つのスキル
DX推進の担当者・リーダーなどを任命する組織が増えています。
デジタルの専門家のための知識ではありません。組織内のDXを推進する担当者・管理者の方をバックアップするべく生まれた研修を集めました。
対象
- 組織内のDXを推進する担当者・管理者の方
- デジタルツールの導入を主導する立場にある方
セットでおすすめの研修・サービス
ChatGPTを活用したビジネス文書研修~文書作成の新スタンダードを学ぶ
文書の作成効率を劇的に上げるChatGPTを活用方法を身につけていただきます。
今まで「時間のかかる」業務だった文書作成も、ChatGPTを活用することで劇的な効率化が期待できます。それにより、中身を考えるクリエイティブな時間に注力することが可能です。
営業向けChatGPT研修~提案書作成・Excel作業を効率化する(半日間)
営業活動の中で、ChatGPTを用いてどのような業務を効率化できるか学ぶ研修です。
使い方を学ぶだけではなく、ChatGPTの回答精度の高め方やプロンプトのテンプレートの紹介など、実践的な活用方法までお伝えします。
UX(ユーザーエクスペリエンス)入門研修
UXを取り入れる目的と目標を設定し、そのゴールに向けた具体的なユーザー像の描き方・UXデザインを作り上げていくための基礎となる考え方を解説します。
上記コラムで身につけておきたい力としてお話していたUIはUXの要素の一部です。
ユーザー部門の担当者、商品企画、システム設計などに携わる方、利用者立場に立った使用感を意識したプロトタイプを作成する商品開発者向けです。