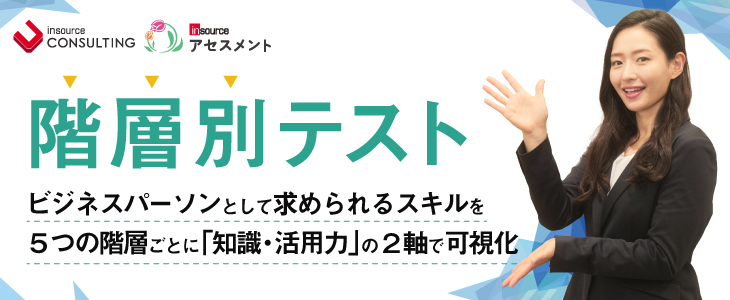指示待ちからの脱却!上司から「デキる」と評価される若手社員の仕事術6選

「最近の若手は指示待ちで困る」
「もっと積極的に動いてほしい」
このような言葉を先輩や上司から言われたことはありませんか。もし心当たりがあるなら、それは「仕事の進め方」にヒントがあるかもしれません。
現代のビジネスでは、与えられた役割をこなすだけでなく、チームに主体的に貢献し、質の高い仕事をスピーディーに完遂する能力が求められます。そのためには、一般的に言われる「報連相」だけでは不十分です。この記事では、あなたが真に「デキる」と評価されるための、具体的な6つの仕事術をお伝えします。
「言われたことをやる」のその先へ:指示を「受け止める」技術
「指示通りに動いてほしい」と願う上司の方は多いでしょう。しかし、指示通りに動くだけでは、真のチーム貢献には繋がりません。仕事の第一歩は、正確な指示の受領です。単に話を聞くだけでなく、その場で不明点や疑問を解消することが非常に重要なのです。
3つの質問で指示を「見える化」する
1. 不明点をその場で質問する習慣をつける
上司からの指示に対して、「〇〇について、もう少し詳しく教えていただけますか」と、その場で具体的に質問する習慣をつけましょう。「後で調べます」「たぶん大丈夫です」ではなく、「今、この場で確認します」という意識を持つことで、手戻りを未然に防ぎます。
2. 指示の「背景」と「目的」を確認する
指示された作業の背景にある意図や、その仕事が最終的にどのような成果に繋がるのかを上司に確認しましょう。「この仕事は、最終的にどのような状態を目指しているのでしょうか」と質問します。与えられた業務を、単なる作業ではなく、目的意識を持って取り組むようにします。
3. 復唱と確認で「認識のズレ」をなくす
指示の内容を、若手社員が自分の言葉で復唱し、上司に確認する習慣をつけましょう。「〇〇という認識で合っていますか」と確認することで、指示の受け止め方のズレを防ぎます。
「納期を守る」だけでは不十分:品質とスピードを両立する計画術
上司から計画を立てるよう指示されたとき、とりあえずスケジュールを組んで満足していませんか。重要なのは「品質や納期を意識した計画立案」です。単に納期を守るだけでなく、求められる品質を担保しながらスピーディーに完遂できるような計画を立てることで、ワンランク上の仕事ができます。
3つの思考法で計画精度を極める:逆算・期待値・リスク予測
1. 「逆算思考」でスケジュールを組む
「〇日までに完了」という指示があった場合、「そこから逆算して、いつまでに何を終わらせる必要があるか」を考えましょう。例えば、資料作成であれば、構成案の作成・情報収集・執筆・レビューといった各工程にどれくらいの時間を要するのかを具体的に見積もることが重要です。
2. 上司の期待値を計画に盛り込む
計画段階で、「この成果物で、上司は何を期待しているのだろう」と考えましょう。「情報をどこまで盛り込むべきか」「どのような粒度で報告すべきか」といった上司の期待値を推測します。必要であれば事前に確認することで、手戻りを減らし、質の高い成果物に繋げます。
3. 想定されるリスクを3つ挙げる
計画を立てる際に、想定されるトラブルやリスクを具体的に3つ挙げましょう。例えば、「情報収集に時間がかかる」「急な別件対応が入る」などです。そして、それぞれのリスクに対する対応策も同時に検討することで、計画の精度が高まります。
「困ったら相談」を越えて:自ら「解決策を探る」主体性
仕事を進める中で、不明点や問題に直面することは避けられません。その際に「一人で抱え込まず、早めに解決策を探る姿勢」が大切です。これは「とりあえず上司に相談したらいい」ということではありません。自ら仮説を立て、解決策を検討する「主体性」が求められます。
代替案の提示と深堀力で問題解決力を高める
1. 「3つの解決策」を持って相談する
問題に直面した際、「どうしたらいいですか」と丸投げするのはNGです。「A案・B案・C案の3つの解決策を考えたのですが、どれが良いでしょうか」と、具体的な選択肢を持って相談しましょう。これにより、単なる「相談」から「問題解決への提案」へとレベルアップすることができます。
2. 「なぜうまくいかないのか」を深掘りする
問題が発生したときに、「なぜうまくいかないのか」「何が原因なのか」を自分自身で深掘りして考えましょう。単なる表面的な事象だけでなく、その根源にある課題を見つける力を養うことで、より本質的な解決に繋がります。
「終わりました」だけではもったいない:成果の質を高める中間報告

中間報告は、上司が状況を把握し、必要なアドバイスを提供するための貴重な機会です。単なる進捗報告で終わってはもったいないです。中間報告は、手戻りを防ぎ、連携を強化し、最終的な成果物の品質を高めるための重要なプロセスなのです。
「成功と課題」+「今後のTODO」で中間報告の質を高める
1. 「うまくいっている点」と「課題点」を具体的に報告する
中間報告の際に、「どこまで進んでいるか」だけでなく、「うまくいっている点」と「課題となっている点」を具体的に報告しましょう。例えば、「Aの部分は想定通り進んでいますが、Bの部分で〇〇という問題が発生し、解決策を検討中です」というように、具体的に報告します。このことは、上司が的確なアドバイスをする上で非常に有効です。
2. 「次の一手」を明確に共有する
中間報告の締めくくりに、「この後は〇〇を進めていきます」と、次に行うことを明確に共有しましょう。次の業務が明確になり、上司も安心して仕事を任せることができます。
「ミスがないか」の確認を超えて:期待との「ズレ」をなくす最終確認
仕事の完了が近づいたら、成果物の最終確認は必須です。この際、単に「ミスがないか」を確認するだけでなく、「上司や先輩が期待する成果と、実際にできあがったものとの間にズレがないか」を慎重に確認することが重要です。
2つの視点で最終チェックの精度を上げる
1. 「上司になったつもり」で成果物を確認する
若手社員に、作成した成果物を「もし自分がこの仕事の依頼者だったら」という視点で見直しましょう。「この資料で、求めていた情報が網羅されているか」「この報告書で、疑問点は解消されるか」といった視点で確認することで、客観的な視点を養うことができます。
2. セルフフィードバックの習慣化
最終確認の際に、「今回の仕事で特に工夫した点は何か」「もしもう一度やるとしたら、どこを改善するか」といったセルフフィードバックをする習慣をつけましょう。これにより、内省を通じて自身の成長を促すことができます。
「終わりました」で終わらせない:学びと成長を繋ぐ終了報告
最終的な確認が完了したら、上司や先輩に終了報告を行います。これは単なる「終わりました」という報告ではなく、業務を通じて得られた学びや、今後の改善点などを添えることで、自身の成長を示す機会にもなります。
三要素を盛り込んだ終了報告で成長をアピールする
1. 「気づき」と「学び」を言語化する
終了報告の際に、「今回の仕事で特に印象に残ったこと」「新たに学んだこと」を具体的に報告しましょう。例えば、「〇〇の資料作成を通じて、情報収集の効率的な方法を学びました」といった具体的な学びを報告します。これにより、上司に自身の成長を印象付けることができます。
2. 「課題」と「改善点」を明確にする
今回の業務で感じた課題や、次回以降に改善したい点を具体的に報告しましょう。「〇〇の部分は、もっと効率化できると感じました。次回は××を試してみたいです」など、具体的な行動計画も盛り込むと良いでしょう。
3. 「次に活かすこと」を宣言する
「今回の経験を、次回〇〇の仕事に活かしていきたいです」と、今後の業務への意欲や具体的な行動を宣言しましょう。これにより、自身の成長意欲を上司に伝え、次なる成長の機会へと繋げることができます。
上司から「デキる若手」と評価されるために
上記6つの仕事術を身につけている人は、主体的にチームに貢献する「デキる」若手として評価されます。これらのスキルは、日々の業務を通じて実践と内省を繰り返すことで深まりますが、体系的な学びもまた、成長を加速させます。
インソースでは、皆さんがこれらのスキルを効率的に習得し、より良い仕事の進め方を通じてチームに貢献できるビジネスパーソンへと成長していくための、多岐にわたる研修プログラムをご用意しています。
例えば、「若手社員研修」では目的意識や仮説思考を深め、「仕事の進め方研修」ではコミュニケーションのコツや仕事を計画的かつスムーズに進めるポイントを習得できます。あなたが真にチームに貢献できる「デキる」人材へと成長するために、ぜひインソースの研修プログラムをご検討ください。皆さんの具体的な課題や目的に合わせて、最適な学習機会をご提供します。
若手社員研修~主体性の発揮
若手社員は、今後組織を牽引していくための「仕事の主体者」です。本研修では、この役割を受け入れるために必要な「目的意識」「仮説思考」「判断基準」について習得します。演習では実際に自分の仕事を優先順位付けしたり、数値目標を立てるなど、実務に沿った内容です。
よくあるお悩み・ニーズ
- 指示された業務は一通りこなせるようになったが、本当にこのままで良いのか不安
- 受け身姿勢から脱却したい
- 中核人材に向けてステップアップしたい
本研修の目標
- 「仕事において自身ができていること、できていないこと」を客観的に認め、今後の課題設定ができる
- 自身の仕事における「期待される成果とそれを実現するための過程」を理解して行動できる
- 仕事の優先順位を的確に判断した上で行動ができる
- 自身の仕事にかかわる人・組織と関係を構築し、状況に応じて協力を仰ぐことができる
セットでおすすめの研修・サービス
仕事の進め方研修(1日間)
本研修では、無計画に仕事をしないためのタイムマネジメントスキル、1人で仕事を抱え込まないためのコミュニケーションスキルを学びます。
研修内ではまず、自分の仕事は組織全体の大きな仕事の流れの一部分であることやチームワークが大事であることなどの仕事の捉え方をお伝えします。そのうえで、実際の仕事に活かせます。
【レンタルセットプラン】若手社員向け詰合せ
本サービスは「若手社員」をテーマとした講座を4本セットでレンタル受講可能なパッケージプランです。
主体性発揮・コミュニケーション・PDCAサイクル・タイムマネジメントというプログラムを通じて、若手社員が職場で自信を持ち、効率的に業務を進めるためのスキルを習得できます。
階層別テスト|ビジネスで必要な「知識」と「活用力」を測定するテスト
「階層別テスト」は、若手・中堅・ベテラン・初級管理職・上級管理職に「いま」必要なスキルが一目でわかるアセスメントサービスです。
ビジネスパーソンに求められるスキルを洗い出し、これらのカテゴリ・スキルについてビジネスの場面で必要な「知識」を問うとともに、ケーススタディなどを通じてそれを「活用できる力(活用力)」を有しているかどうかを測定します。